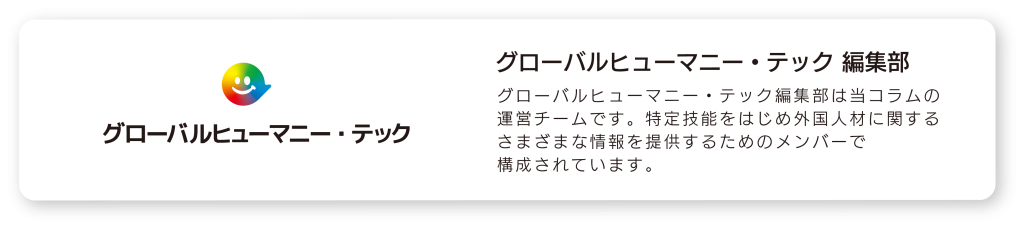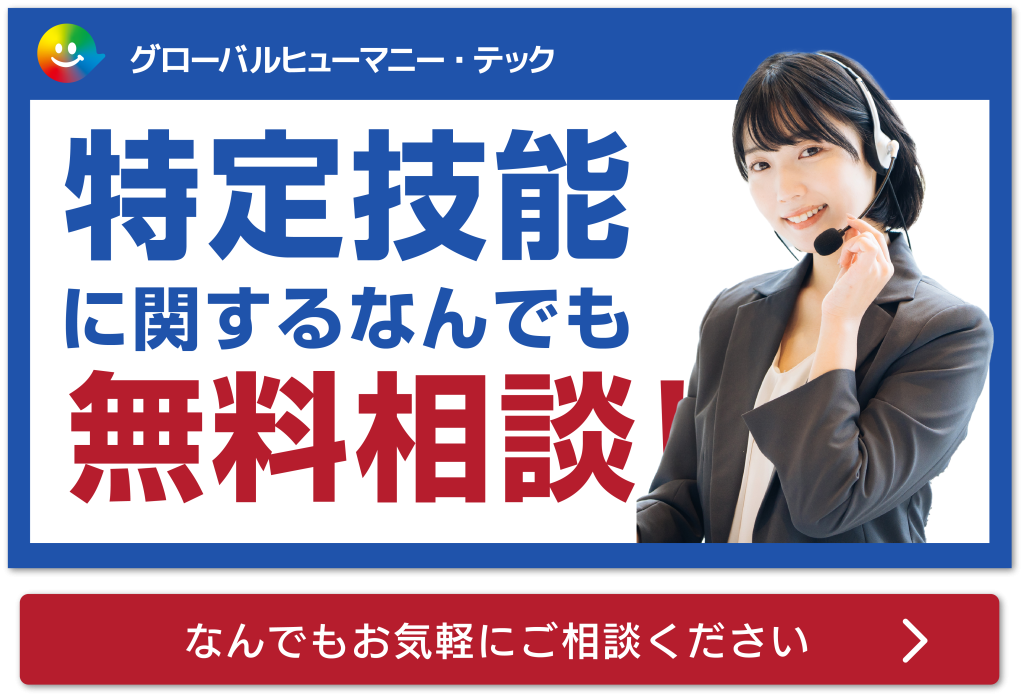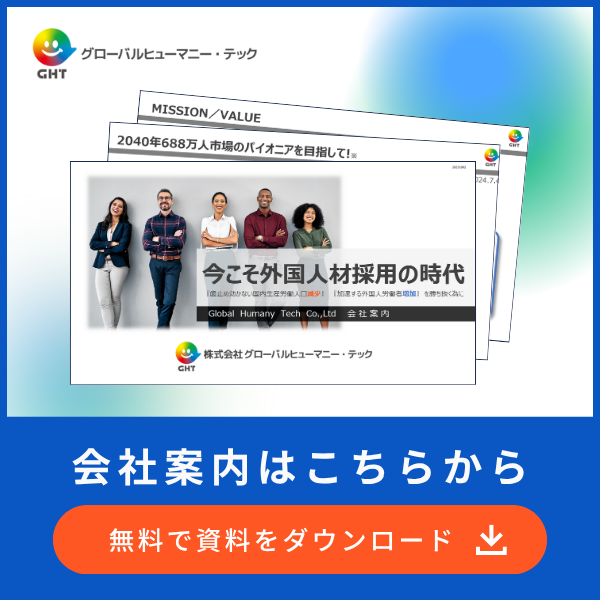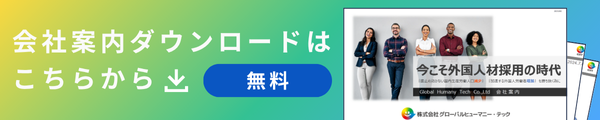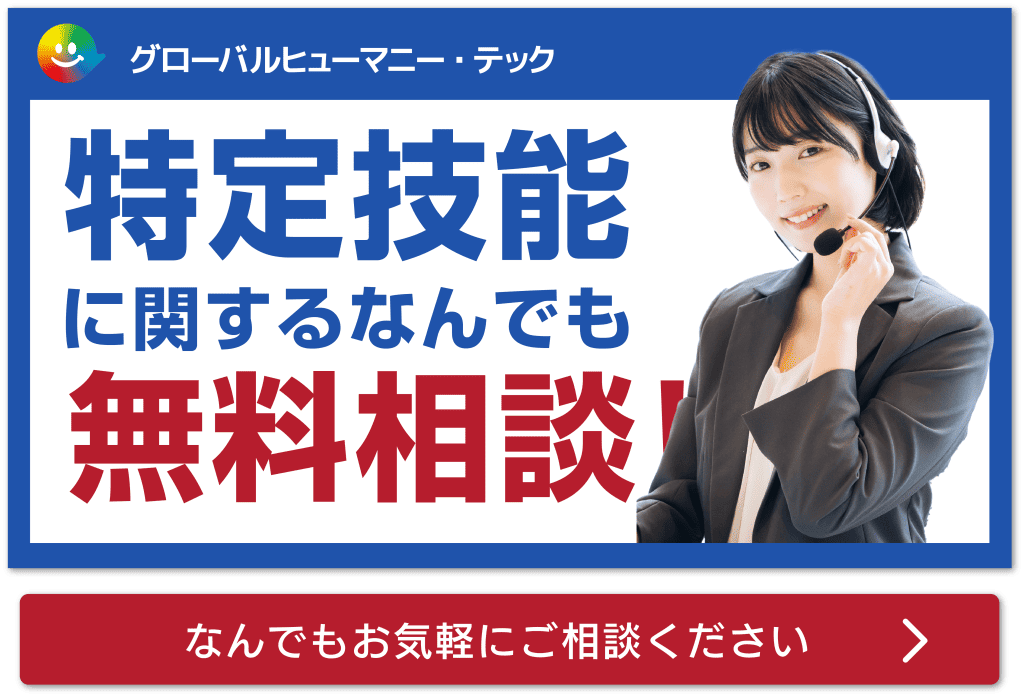人手不足の解消策として、外国人材の採用を検討する企業が増えています。しかし、文化や習慣の違いを理解しないままだと、従業員の些細な行動やSNSへの投稿が、意図せず企業の評判を大きく損なう「レピュテーションリスク」に発展しかねません。
とくに外国人雇用においては、労働環境やコンプライアンスに関する問題が表面化しやすく、一度ネガティブな評判が広まってしまうと、その信頼を取り戻すのは容易ではありません。
この記事では、レピュテーションリスクの具体的な事例を5つ取り上げ、背景にある原因を分析します。さらに、リスクを未然に防ぎ、万が一発生してしまった際に被害を最小限に抑えるための具体的な対策までわかりやすくご紹介します。
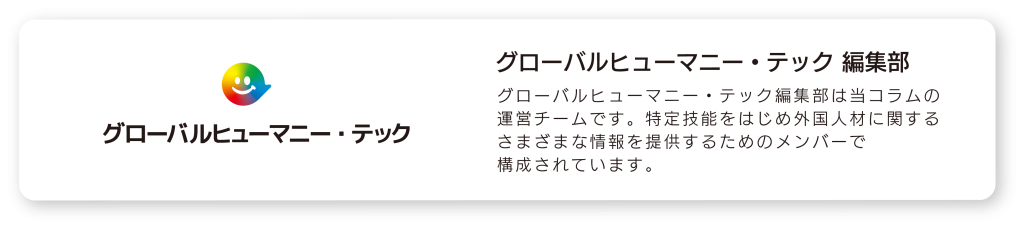
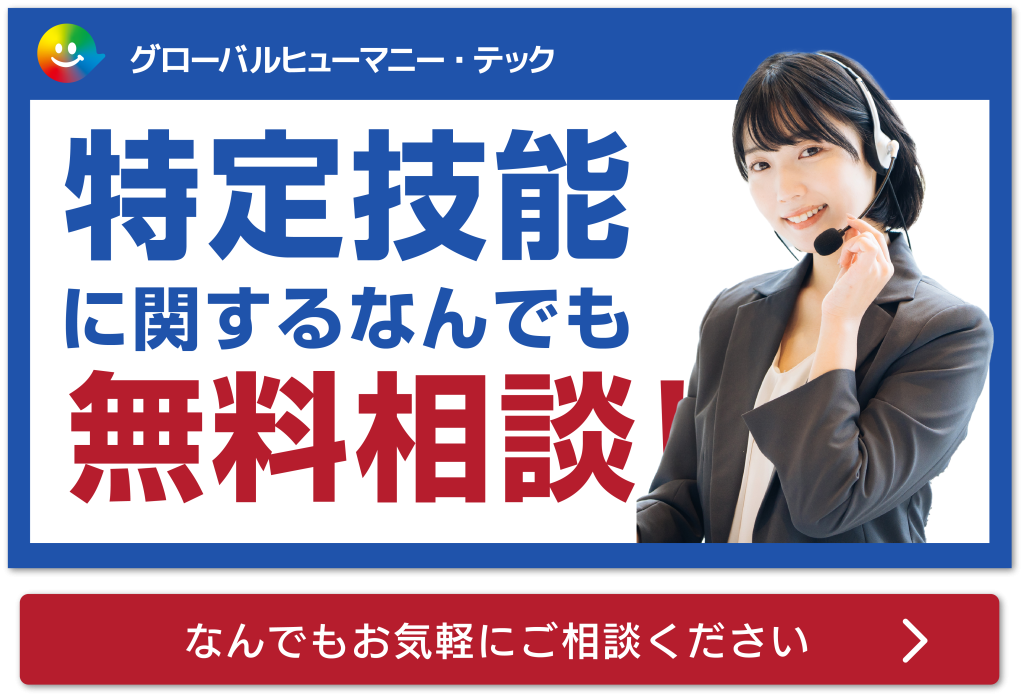
レピュテーションリスクとは?
レピュテーションリスクとは、企業に関するネガティブな評判が広まり、ブランド価値や社会的信用が低下して、経営に悪影響をおよぼす危険性です。具体的には、売上減少や株価下落、優秀な人材の流出、取引先からの契約打ち切りなど、有形無形のさまざまな損失につながる可能性があります。
インターネットやSNSの普及により、情報は瞬時に広範囲に拡散されるようになりました。このため、個人の発信が大きな炎上に発展して、企業の存続を脅かすケースも少なくありません。
事実にもとづかない噂や風評被害だけでなく、実際に起きた製品の欠陥や従業員の不祥事などが原因となるため、すべての企業にとって軽視できない経営課題となっています。

レピュテーションリスクにつながる事例5つ
次は、レピュテーションリスクにつながる事例について紹介します。それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
1.従業員の不適切なSNS投稿による炎上
アルバイト従業員が、勤務先の店舗内にある商品で遊んだり、厨房でふざけたりするなどの不適切な行為の様子を撮影して、SNSに投稿したため炎上するケースです。いわゆる「バイトテロ」と呼ばれる行為は、瞬く間に拡散され、企業の衛生管理や従業員教育の体制に厳しい批判が集中します。
これにより、当該店舗の閉鎖や、企業全体の売上減少、株価下落といった深刻な経済的損失につながる場合が少なくありません。個人の軽率な行動が、企業の社会的信用を根本から揺るがす典型的な事例です。
2.製品・サービスの品質問題や偽装の発覚
食品の産地や賞味期限を偽装していたり、自動車の安全性能に関わるデータを改ざんしていたりなど、製品やサービスの根幹に関わる不正が発覚するケースです。これらの事実は、内部告発や行政の調査によって明らかになる場合が多く、消費者の信頼を大きく裏切る行為と見なされます。
人の健康や安全に関わる問題であった場合、大きな影響をおよぼします。大規模なリコールや生産停止に追い込まれるだけでなく、長期にわたる不買運動や集団訴訟に発展して、築き上げてきたブランド価値が完全に失墜する可能性があります。
3.個人情報の大規模な漏えい
サイバー攻撃や内部の不正アクセスにより、企業が保有する大量の顧客情報が外部に流出してしまうケースです。氏名や住所、クレジットカード情報といった機密性の高い情報が漏えいした場合、被害者への金銭的な補償や謝罪、セキュリティ体制の甘さを厳しく追及されます。
顧客は「この企業は信頼できない」と判断して、サービスから離脱してしまいかねません。また、監督官庁からの行政指導や罰金が科される場合もあり、直接的な損害だけでなく、社会的な信用の失墜という二重のダメージを受けてしまいます。
4.経営陣や幹部の不祥事・コンプライアンス違反
経営トップによる横領や脱税、ハラスメントといったスキャンダルが発覚するケースも深刻なレピュテーションリスクを引き起こしかねません。こうした個人的な問題に加え、外国人労働者の不法就労を認識しながら雇用を続けるといった組織的なコンプライアンス違反も、企業の評判を大きく損ないます。
企業の顔である経営陣の倫理観の欠如は、企業全体のガバナンス体制そのものへの不信感につながります。投資家は株を売り、取引先からは関係を見直され、優秀な従業員は愛想を尽かして離職するなど、ステークホルダー全体からの信頼を失います。トップの個人的な問題が、組織全体の崩壊の引き金となり得る事例です。
なお、不法就労助長罪の事例については、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事:【2025年最新】不法就労助長罪の事例3選|外国人を雇用する際に知っておきたいポイントもご紹介!
5.劣悪な労働環境に関する内部告発
違法な長時間労働やサービス残業の常態化、あるいは職場内でのパワーハラスメントといった劣悪な労働環境が内部から告発されるケースです。在職中や退職した従業員が、実体験を口コミサイトやSNSへ投稿して、情報が拡散される場合が多いです。
「ブラック企業」というネガティブな評判が一度定着してしまうと、企業イメージは著しく悪化します。とくに、言葉や文化の壁から声を上げにくい技能実習生など、外国人労働者を巡る労働環境問題は、企業の評判を著しく損なう原因となり得ます。
その結果、優秀な人材の採用が困難になるだけでなく、既存従業員の士気低下や離職率の増加を招きかねません。最終的には、企業全体の生産性を阻害して、事業の成長基盤そのものを内部から崩壊させる深刻な事態につながるリスクです。
なお、技能実習生に関する主な問題点については、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事:技能実習生に関する主な問題点は5つ|問題が発生する原因や対策を詳しくご紹介します!

レピュテーションリスクが発生する原因3つ
レピュテーションリスクは、さまざまな要因が複雑に絡み合って発生しますが、その根源をたどると、大きく3つの原因に分類できます。それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
1.デジタル技術の進化とSNSの普及
現代社会では、スマートフォンとSNSの普及により、誰もが簡単に情報発信者となれる時代です。個人の発信した情報が、共感を呼んだり、批判の対象となったりして、瞬時に世界中に拡散される可能性があります。
企業にとって、顧客や従業員によるポジティブな口コミが広がる点ではメリットとなります。しかし、1つのネガティブな投稿が大規模な炎上を引き起こして、コントロール不能な形で評判を落とすというリスクと常に隣り合わせの状態です。
情報の拡散スピードと範囲の増大が、レピュテーションリスクの根本的な原因の1つといえます。
2.コンプライアンス・ガバナンス体制の不備
法令遵守(コンプライアンス)の意識の欠如や、経営を監視・監督する仕組み(コーポレート・ガバナンス)が十分に機能していない点も、リスクを発生させる原因です。
たとえば、製品の品質管理基準が曖昧であったり、従業員に対するハラスメント防止の研修が不十分であったりすると、不正や不祥事が発生しやすくなります。さらに、問題が起きても内部で適切に処理されず、隠蔽体質が蔓延すれば、内部告発で外部に露見して、深刻な信用の失墜を招きます。
3.従業員の意識やリテラシーの不足
企業という組織は、それぞれ働く従業員の集合体のため、従業員の倫理観や情報リテラシーのレベルが、企業全体のレピュテーションリスクに直結します。
会社の機密情報を外部に漏らしたり、SNSの公開範囲の設定を理解せずに私的な投稿を行ったりするなど、個人の意識の低さや知識不足が、意図せずして企業に甚大な損害を与える場合があります。
正社員だけでなく、アルバイトや派遣社員など、多様な雇用形態のスタッフが働く現代においては、全従業員に対する継続的な教育と意識向上の取り組みが不可欠です。
なお、特定技能で実施する生活オリエンテーションについては、こちらの記事で解説しています。
関連記事:【担当者必見】特定技能で実施する生活オリエンテーションとは?具体的な内容や注意点を詳しく解説します!

レピュテーションリスクへの対策は4つ
レピュテーションリスクを完全にゼロにするのは困難ですが、適切な対策を講じれば、リスクの発生を予防して、万が一発生した際の影響を最小限に抑えられます。それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
1.社内規程やマニュアルの整備
行動規範や情報の取り扱いに関するルールを明確に定めた社内規程や、緊急時対応マニュアルの整備が基本です。SNSの利用ガイドラインを策定して、私的な利用であっても企業の一員としての自覚を持つ、他者を誹謗中傷しない、会社の機密情報を漏らさないなどを具体的に明記します。
また、炎上や情報漏えいなどのクライシスが発生した際の報告ルート、対外的な情報発信の手順、責任者などを定めた危機管理マニュアルを準備しておくと、迅速かつ冷静な対応ができます。
2.従業員への継続的な教育・研修
ルールやマニュアルを整備するだけでは不十分であり、内容を全従業員に浸透させなければなりません。コンプライアンス研修や情報セキュリティ研修、SNSリテラシー研修などを定期的に実施して、レピュテーションリスクの重要性や具体的な事例を共有しましょう。
なぜ、そのルールが必要なのか、違反した場合にどのような結果を招くのかを理解させれば、従業員の当事者意識を高められます。座学だけでなく、具体的なケーススタディを用いたディスカッションを取り入れると、より実践的な学びにつながります。
3.ネット上の情報監視(モニタリング)体制の構築
自社や自社製品・サービスについて、ネット上でどのような口コミや評判が語られているかを日常的に把握しておくと、リスクの早期発見につながります。
SNSや掲示板、ブログなどを定期的に監視(ソーシャルリスニング)しておくと、いち早く察知できます。初期段階で火種を発見できれば、炎上に発展する前に、投稿者への丁寧な説明や、公式サイトでの正確な情報発信といった対応が可能です。
また、専門のツールを導入したり、外部の専門業者に委託したりする方法も効果的な手段です。
4.危機発生時の誠実かつ迅速な対応
どれだけ予防策を講じても、リスクが顕在化してしまう可能性はあるため、問題が発生してしまった後の対応が欠かせません。まず、事実関係を迅速かつ正確に調査して、何が起きているのかを把握しましょう。
隠蔽せずに、誠実な態度で謝罪や説明を行えば信頼回復につながります。また、自社のウェブサイトやプレスリリースなどを通じて、企業としての公式見解を明確に、すみやかに発信するように心がけてください。
対応が遅れたり、責任逃れと受け取られるような態度をとったりすると、より炎上を招き、被害を拡大させてしまいます。

外国人採用の相談に「グローバルヒューマニー・テック」がおすすめな理由
株式会社グローバルヒューマニー・テックでは、グローバル人材に対する総合的な生活支援を実施しています。豊富な実績による盤石なサポート体制とIT技術をかけ合わせた独自のノウハウで、外国人労働者の支援プラットフォームを充実させています。
外国人材の安心安全な採用支援はもちろん、就業支援や生活支援を通じて人手不足をグローバルソリューションで解決するのが私たちの使命です。⇒株式会社グローバルヒューマニー・テックに相談する

レピュテーションリスクでよくある3つの質問
最後に、レピュテーションリスクでよくある質問について解説します。それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
質問1.レピュテーションリスクと風評被害の違いは何ですか?
レピュテーションリスクは、実際に起きた不祥事や製品の欠陥、不誠実な対応など「事実」を原因とする評判の低下リスクを含む広い概念です。一方、風評被害は、事実無根の噂やデマといった「虚偽の情報」によって評判が下がります。
このため、風評被害はレピュテーションリスクの一種と位置づけられます。しかし、レピュテーションリスクは事実にもとづくものも含む、より包括的なリスクという点が相違点です。
質問2.リスクが発生した場合、どこに相談すればよいですか?
レピュテーションリスクが顕在化した場合、自社内だけで対応するのは困難なケースが多いです。まずは、顧問弁護士に相談し、法的な観点からのアドバイスを求めましょう。
誹謗中傷に対しては、法的手続きが必要になる場合があります。また、広報対応やメディアリレーションズに関してはPR会社、ネット上の炎上対応やネガティブ情報の監視・削除に関しては専門の対策会社など、事案に応じて外部の専門家の力を借りましょう。
これにより、事態の沈静化と信頼回復への近道につながります。
質問3.中小企業でも対策は必要ですか?
企業規模の大小にかかわらず、レピュテーションリスクはすべての企業に存在します。経営資源の限られる中小企業こそ、一度評判が落ちると売上への影響が大きく、回復が困難になる可能性があります。
近年、SNSの普及により、中小企業の活動も簡単に世の中に知られるようになりました。大企業のような専門部署の設置は難しくても、経営者自身がリスクを正しく認識して、従業員教育や最低限のマニュアル整備など、できる範囲から対策をはじめましょう。

まとめ
レピュテーションリスクは、SNSの普及した現代において、すべての企業が真摯に向き合うべき経営課題です。従業員の不適切な投稿や製品の品質問題、情報漏えいなど、発生原因は多岐にわたります。
これらのリスクは、一度発生すると企業のブランド価値や社会的信用を著しく毀損して、回復には多大な時間とコストを要します。リスクを他人事と捉えず、自社にも起こりうることとして認識しなければなりません。
社内規程の整備や継続的な従業員教育、ネット上のモニタリング体制の構築といった予防策を地道に進める方法が、企業の持続的な成長を守るポイントになります。
なお、株式会社グローバルヒューマニー・テックでは、グローバル人材に対する総合的な生活支援を実施しており、外国人の受け入れにおける豊富な経験と知識を有しています。ご相談・お見積りはもちろん無料です。まずはお気軽にお問合せください。⇒株式会社グローバルヒューマニー・テックに相談する