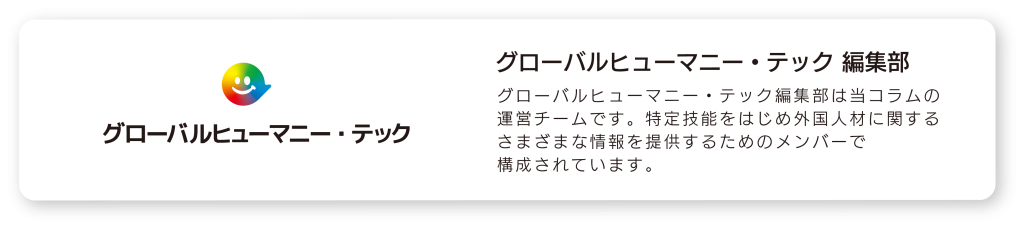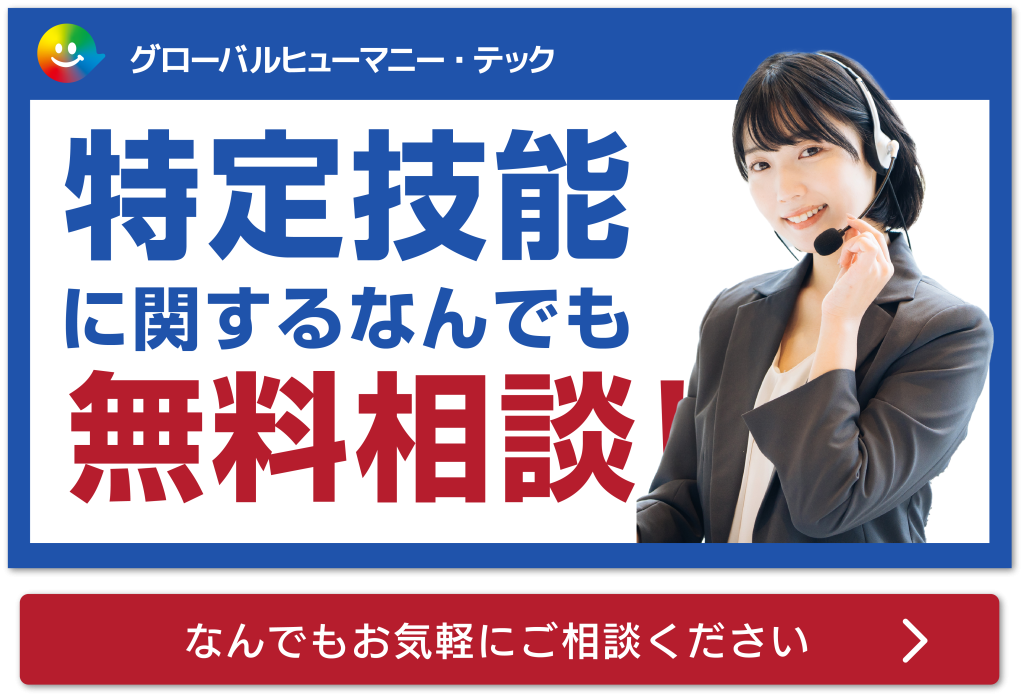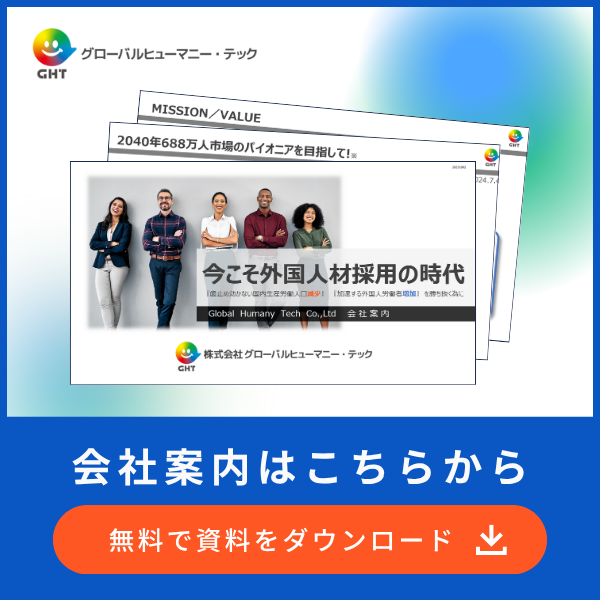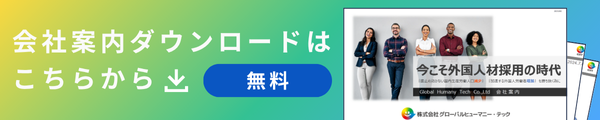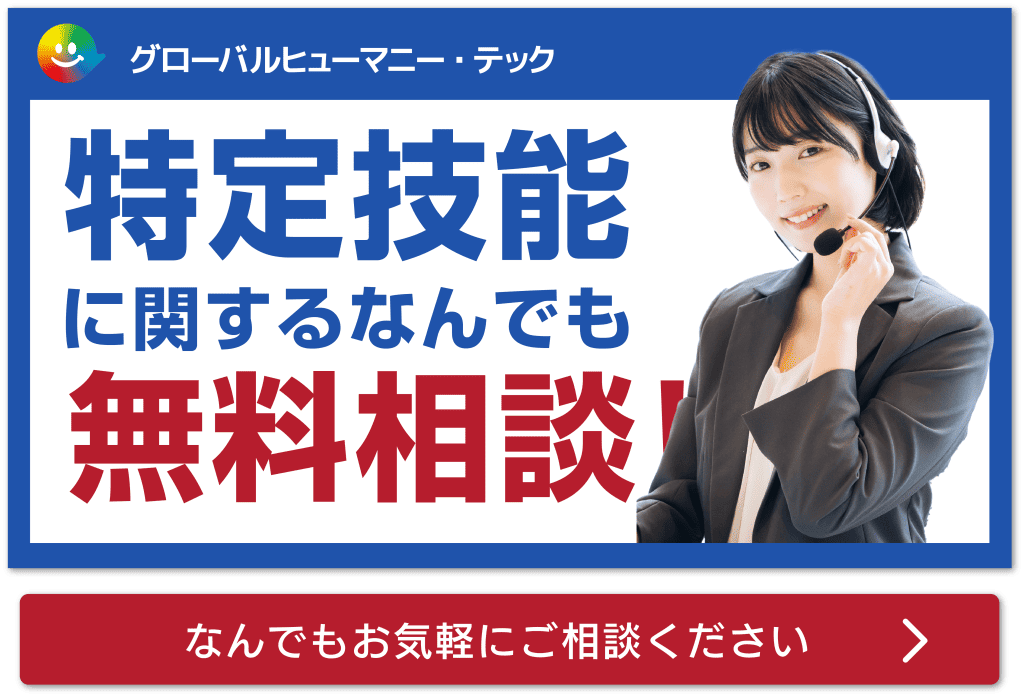外国人材の採用にあたって、「在留資格認定証明書」の取得が必要なのか、どのように進めればよいか不安に感じる方もおられるのではないでしょうか。
「在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility: COE)」は、日本に入国しようとする外国人の活動内容が虚偽ではないと証明するものです。
このため、外国人材を雇用するには、原則としてこの証明書の取得が最初の関門となります。
手続きが遅れると、入社時期がずれ込むなど、採用計画全体に影響が出かねません。
スムーズな採用を実現するための具体的なステップは以下の通りです。
- ステップ①必要書類の準備
- ステップ②申請理由書の作成
- ステップ③出入国在留管理庁への申請
- ステップ④審査期間と結果の通知
- ステップ⑤ビザ(査証)の取得
この記事では、在留資格認定証明書の基本から、申請・取得までの具体的な流れを詳しく解説します。また、よくある質問も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
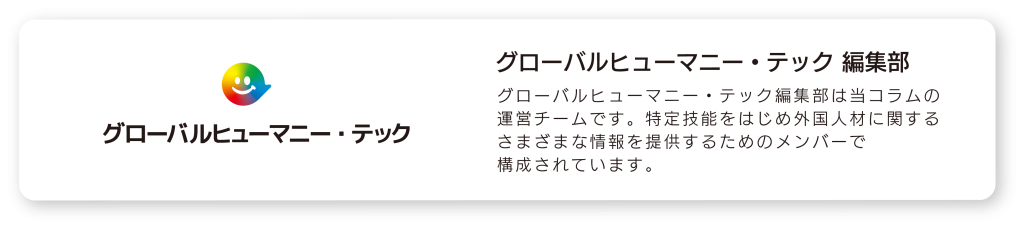
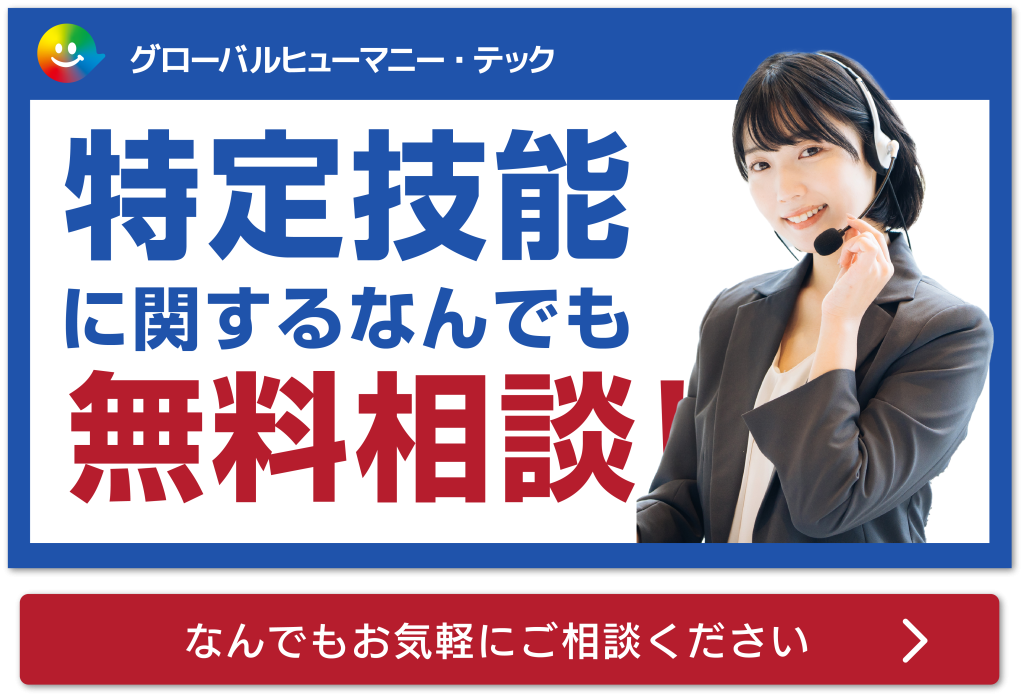
在留資格認定証明書の基本的な3つの知識
まず、在留資格認定証明書の基本的な知識を紹介します。 それぞれ詳しくみていきましょう。
基本①在留資格認定証明書(COE)の役割
COEの最大の役割は、日本国外にいる外国人の入国審査手続きを簡素化して、迅速化する点にあります。
COEは、「この外国人は、日本で活動する資格がありますよ」という法務省のお墨付きのようなものです。
これがなければ、在外公館がゼロからその外国人の活動内容や受け入れ企業の信頼性を審査しなければならないため、膨大な時間がかかってしまいます。
COEは、審査の大部分を日本国内で事前に済ませておくための制度です。
基本②在留カードとの違い
混同されやすいものに「在留カード」がありますが、これはCOEとはまったく異なるものです。
以下の表にCOEと在留カードの違いについてまとめました。
◆COEと在留カードの違い
| 項目 | 在留資格認定証明書(COE) | 在留カード |
| 対象者 | 日本に入国しようとする外国人 | 日本に中長期(3か月超)在留する外国人 |
| 発行者 | 出入国在留管理庁(日本国内) | 空港(入国時)または出入国在留管理庁 |
| 役割 | ビザ(査証)発給と入国審査を迅速 化する | 日本在留中の身分証明書 |
| 形状 | 紙の証明書 | 顔写真付きのカード |
このように、COEは「日本入国のための推薦状」、在留カードは「日本滞在中の身分証明書(運転免許証のようなもの)」とイメージすると分かりやすいです。
なお、在留カードの更新については、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事:在留カードの更新はいつからできる?更新の方法や期限が切れた場合の対象方法を徹底解説!
基本③有効期限とオンライン申請の可否
COEには、発行から3か月間という有効期限があるため、期間内に日本に入国しなければ、COEは失効してしまいます。
交付されたらすみやかに本人へ送付して、ビザ申請と渡航準備を進めてもらわなければなりません。
また、2020年3月から、一部の在留資格(カテゴリー1または2に該当する企業など)については、オンラインでのCOE申請が可能になりました。オンライン申請は、窓口に出向く手間が省け、処理が早い傾向があるなどのメリットがあります。
参考:「在留申請のオンライン手続」|出入国在留管理庁

在留資格認定証明書を取得するための5つのステップ
在留資格認定証明書(COE)の申請から取得までは、以下のステップで進みます。人事担当者として、それぞれのステップで何を行うべきかを正確に把握しておきましょう。
ステップ①必要書類の準備
まず、申請に必要な書類を揃えます。
必要書類は、外国人材が従事する業務内容(技術・人文知識・国際業務、特定技能など)や、企業の規模(カテゴリー)によって異なります。
たとえば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請する場合、一般的に以下の書類が必要です。
◆主な必要書類の例
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、切手を貼付)
- 雇用契約書の写し
- 申請理由書(次のステップで解説)
- 本人の学歴や職歴を証明する書類(卒業証明書、職務経歴書など)
- 受け入れ企業(貴社)の登記事項証明書、直近年度の決算報告書の写し など
企業は、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の提出状況により、4つのカテゴリーに分類されます。このカテゴリーによって、提出が省略できる書類もあります。
参考:「在留資格「技術・人文知識・国際業務」」|出入国在留管理庁
ステップ②申請理由書の作成
申請理由書(または雇用理由書)は、COE申請において非常に大切な書類の1つです。
法定の提出書類ではありませんが、審査をスムーズに進めるため、添付を強く推奨します。
この書類では、「なぜ、その外国人材を雇用する必要があるのか」を具体的に説明します。単に「人手不足だから」ではなく、本人のスキルや経験が、貴社のどの業務でどのように活かされるのかを明確に記載してください。
たとえば、「当社の海外事業拡大に伴い、〇〇国(本国)の市場開拓を担当する人材として、現地での実務経験と語学力を有する〇〇氏が不可欠である」といった具体的な理由が求められます。
ステップ③出入国在留管理庁への申請
書類がすべて揃ったら、原則として受け入れ企業(貴社)の所在地を管轄する出入国在留管理庁(地方局)に申請します。
申請は、企業の職員(人事担当者など)が代理で行えます。
申請にかかる手数料(費用)は、COEが交付される時点では発生しません。しかし、申請を行政書士などに依頼する場合は、別途報酬が必要です。
ステップ④審査期間と結果の通知
申請が受理されると、出入国在留管理庁で審査が開始されます。
標準的な審査期間は、申請内容や時期にもよりますが、おおむね1か月から3か月程度です。
審査期間中は、追加の書類提出を求められる場合も少なくありません。
また、審査が完了すると、結果が郵送(申請時に提出した返信用封筒)で通知されます。許可された場合は「在留資格認定証明書(COE)」が送付され、不許可の場合は「不交付通知書」が届く流れです。
ステップ⑤ビザ(査証)の取得
COEが交付されたら、速やかに海外にいる外国人材本人へ原本を送付します。
国際郵便(EMSなど追跡可能な方法)を利用する場合が一般的です。
COEを受け取った本人は、それを持って自国(または居住地)の日本国大使館や総領事館でビザ(査証)の申請を行います。
COEがあればビザ審査は迅速に行われ、ビザが発給されると、日本へ入国(赴任)が可能となります。
なお、就労ビザの取得方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事:就労ビザの取得方法とは?取得に必要な書類や審査にかかる期間について詳しく解説します!

外国人採用の相談には「グローバルヒューマニー・テック」がおすすめな理由

株式会社グローバルヒューマニー・テックでは、グローバル人材に対する総合的な生活支援を実施しています。豊富な実績による盤石なサポート体制とIT技術をかけ合わせた独自のノウハウで、外国人労働者の支援プラットフォームを充実させています。
在留資格認定証明書(COE)の申請は、外国人採用の第一歩ですが、その後の入社手続き、住居の確保、銀行口座の開設、携帯電話の契約など、外国人材が日本で生活して、活躍するためには多くのサポートが必要です。
外国人材の安心安全な採用支援はもちろん、就業支援や生活支援を通じて人手不足をグローバルソリューションで解決することを使命としています。複雑な手続きや受け入れ体制の構築にお悩みの際は、ぜひ一度ご相談ください。⇒株式会社グローバルヒューマニー・テックに相談する

在留資格認定証明書でよくある3つの質問
最後に、在留資格認定証明書でよくある質問をご紹介します。それぞれ詳しくみていきましょう。
質問①申請が不交付になった場合はどうすればよいですか?
万が一、申請が不交付となった場合は、出入国在留管理庁に不交付の理由を確認しに行けます(原則として申請者または代理人のみ)。
理由を確認して、その問題点をクリアできるのであれば、書類を整備して再申請できます。
不交付の理由としては、申請内容(職務内容)と本人の学歴・職歴との関連性が薄い、企業の安定性に懸念がある、などさまざまです。理由を正確に把握して、対策を講じなければなりません。
質問②転職者の場合も在留資格認定証明書は必要ですか?
すでに日本国内に在留して、有効な在留資格(就労可能なもの)を持っている外国人を中途採用する場合は、COEの申請は不要です。
しかし、転職したり、留学生が就職したりする場合、「在留資格変更許可申請」が必要となるケースがあります。
また、「就労資格証明書」の取得が必要となる場合もあります。これは任意ですが、企業側が適法に就労できるか確認するために有効です。現在の在留カードの資格と有効期限を必ず確認してください。
質問③審査を早くしてもらう方法はありますか?
出入国在留管理庁へ審査を早めるように個別の依頼は、原則としてできません。
審査は申請順に公平に行われます。
しかし、いくつかの工夫で審査がスムーズに進む可能性があります。
たとえば、申請書類に不備がないようにして、申請理由書で採用の必要性を明確に説明しましょう。
さらに、オンライン申請(対象企業の場合)を活用する方法も、早期の交付につながる可能性があります。
なお、外国人採用における注意点については、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事:外国人採用における注意点は7つ|採用動向やメリット・デメリット、採用ステップをご紹介!

在留資格認定証明書の申請を成功させ、スムーズな採用を実現しよう!
在留資格認定証明書(COE)の取得は、外国人材を海外から受け入れるための大切なスタートラインです。
採用計画を滞りなく進めるためには、以下のステップを確実に実行する必要があります。
- ステップ①必要書類の準備
- ステップ②申請理由書の作成
- ステップ③出入国在留管理庁への申請
- ステップ④審査期間と結果の通知
- ステップ⑤ビザ(査証)の取得
COE申請は、必要書類が多く、審査にも時間がかかるため、人事担当者にとっては負担の大きい業務です。しかし、ここをスムーズに乗り越えれば、優秀な外国人材の早期活躍につながります。
なお、株式会社グローバルヒューマニー・テックでは、グローバル人材に対する総合的な生活支援を実施しており、外国人の受け入れにおける豊富な経験と知識を有しています。ご相談・お見積りはもちろん無料です。まずはお気軽にお問合せください。⇒株式会社グローバルヒューマニー・テックに相談する