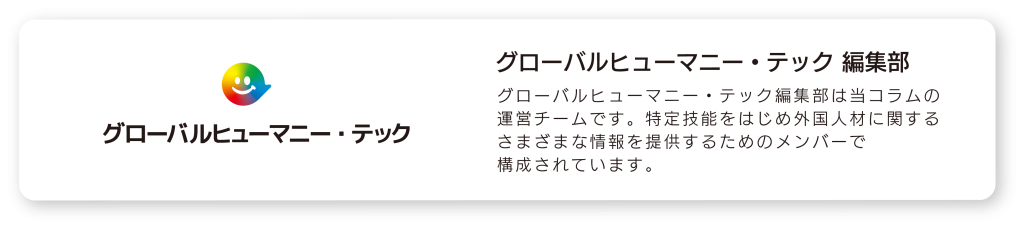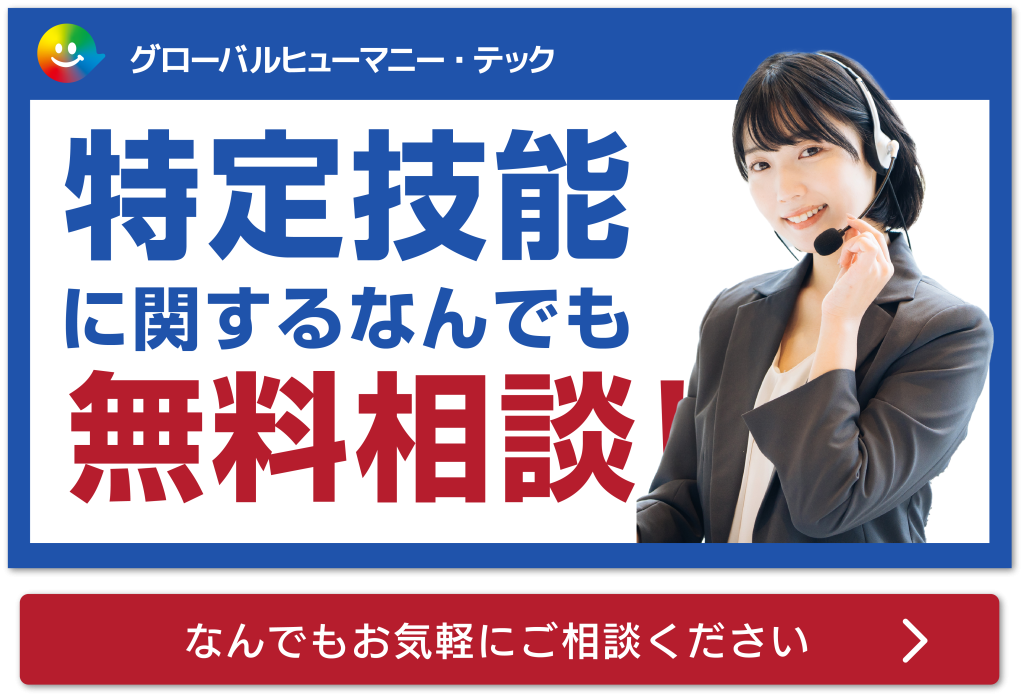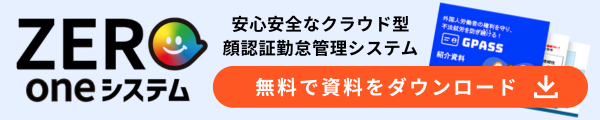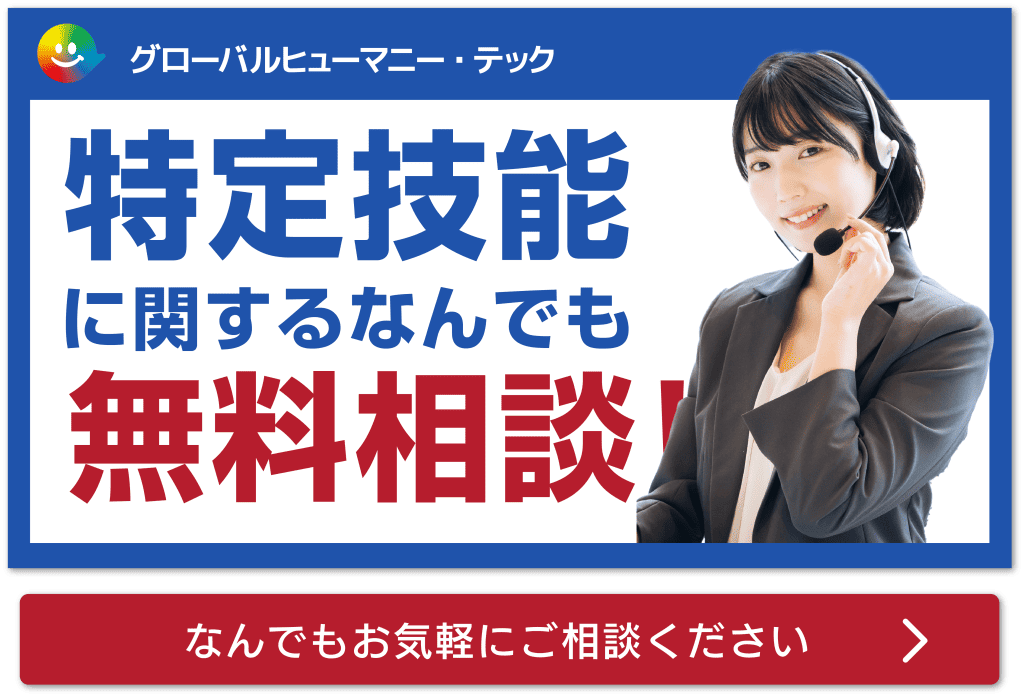年末調整の時期が近づくと、「外国人従業員の年末調整は、日本人との違いは?」「海外に住む家族を扶養に入れる場合、どんな書類が必要?」といった疑問や不安を抱える人事・労務担当者の方も多いのではないでしょうか。
外国人の年末調整は、従業員が「居住者」か「非居住者」かによって扱いが異なります。さらに、扶養控除の適用には厳格なルールが定められているため、注意しなければなりません。
この記事では、外国人の年末調整を行う際に必ず押さえるべき対象者の区分から、必要書類、手続きの具体的な注意点までを分かりやすく解説します。また、年末調整の対象外となるケースやよくある質問も解説していますので、ぜひ参考にしてください。
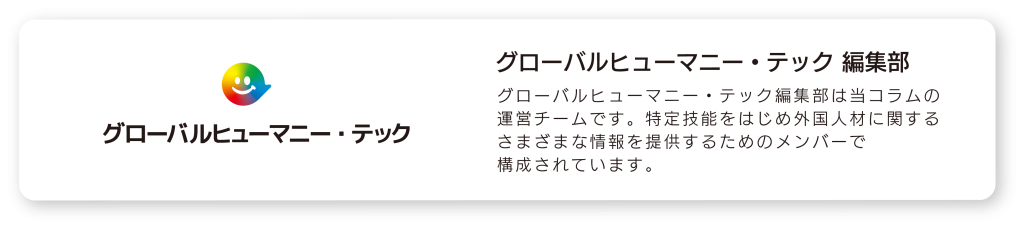
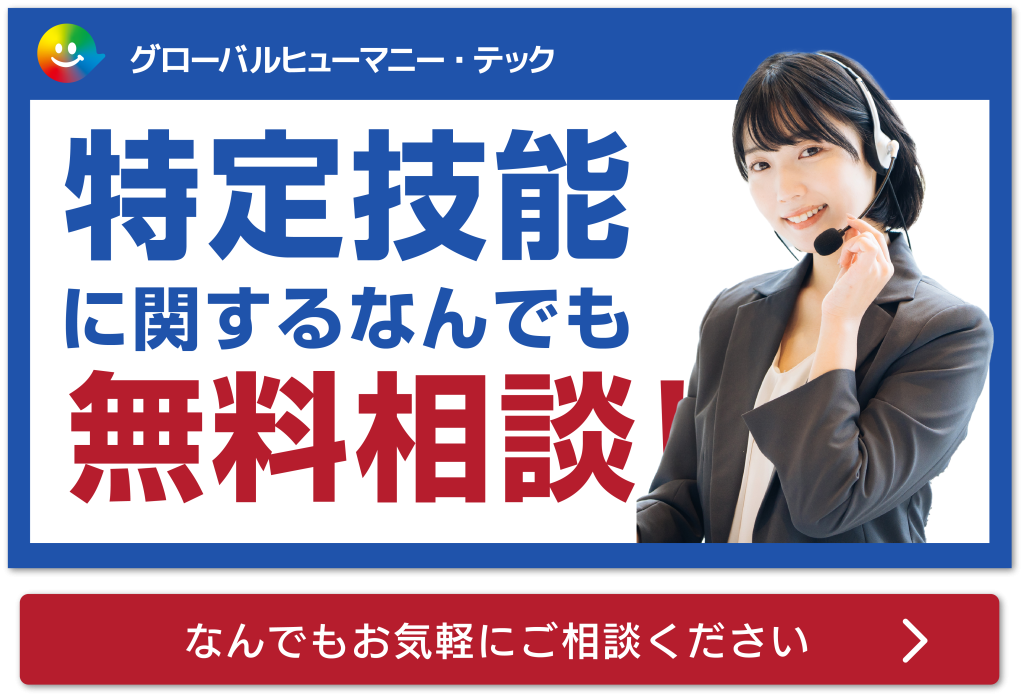
外国人の年末調整でまず確認すべき2つの区分
外国人の年末調整を行う際に、対象の従業員が所得税法上の「居住者」と「非居住者」のどちらに該当するかを正確に判定しなければなりません。この区分によって、年末調整の対象となる所得の範囲や、適用できる控除が大きく異なるため、大切なステップとなります。
1.「居住者」の定義と年末調整の範囲
「居住者」とは、国内に「住所」を持っているか、または現在まで引き続いて1年以上「居所」を有する個人です。外国人の従業員であっても、この要件を満たせば、日本人と同様に「居住者」として扱われます。
居住者の場合、年末調整の対象となるのは、その年の支払いが確定した給与の総額です。これは、国内で得た給与だけでなく、海外勤務で得た国外源泉所得も含む「全世界所得」を指します。
扶養控除、生命保険料控除などのそれぞれ所得控除も日本人と同様に適用も可能です。
2.「非居住者」の定義と年末調整の扱い
「非居住者」とは、「居住者」以外の個人です。たとえば、短期の契約で来日している場合や、海外に生活の拠点を置いたまま一時的に日本で勤務している場合などが該当します。
非居住者は、原則として年末調整の対象にはなりません。彼らの所得に対する課税は、日本国内で得た「国内源泉所得」に対してのみ行われる点が特徴です。
租税条約による特例がある場合を除き、原則20.42%の税率による源泉徴収で完結します。このため、非居住者の従業員に対しては、年末調整を行う必要はなく、源泉徴収票の交付も不要です。

年末調整の対象となる外国人の要件
従業員が「居住者」に該当する場合でも、すべての人が年末調整の対象となるわけではありません。これは日本人の従業員と同様の基準ですが、外国人従業員の場合は入社や退社のタイミングが多様であるため、改めて要件を確認しておきましょう。
1.扶養控除等申告書の提出
年末調整の対象となる大前提は、その年の最初の給与支払い日の前日までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出している点です。この申告書は、配偶者控除や扶養控除、障害者控除などを受けるために必要な書類です。
外国人従業員の場合、書類の記載内容や控除対象となる家族の範囲について誤解が生じやすいポイントでもあります。また、海外に住む家族を扶養に入れる場合は、特別な書類が必要となるため、早めにアナウンスして、準備を促さなければなりません。
2.年間の給与総額(2,000万円以下)
年間の主たる給与の総額が2,000万円を超える従業員は、年末調整の対象外となります。これは国籍に関わらず適用されるルールです。
高額な給与所得者は、年末調整ではなく、翌年に自身で確定申告を行う必要があります。また、年の途中で入社した従業員の場合、前職の源泉徴収票の提出が必要です。前職が海外の企業であった場合、その所得は年末調整の対象に含められないため、注意しなければなりません。

外国人の年末調整の扶養控除における3つの確認事項
外国人の年末調整において、手続きが複雑で、税務調査でも指摘されやすい項目が「扶養控除」の扱いです。要件を満たさないと控除が否認される可能性があるため、慎重な確認が求められます。
1.控除対象となる扶養親族の範囲
扶養控除の対象となるのは、従業員と生計を一にする配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)で、年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)の人です。
これは国内に住む親族でも、国外に住む親族でも共通です。しかし、国外に住む親族を扶養に入れる場合は、その関係性を証明する「親族関係書類」と、生活費などを送金した事実を証明する「送金関係書類」の提出が義務付けられています。
2.国内に居住する親族の場合
従業員が扶養する家族が、従業員本人と同じく日本国内に居住している場合は、基本的に日本人の従業員と同様です。たとえば、留学生の子どもや、一緒に来日した配偶者(所得要件を満たす場合)などが該当します。
この場合、家族のマイナンバーを「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載する必要があります。しかし、その家族が独自の収入(アルバイトなど)を得ている場合は、所得要件(合計所得金額48万円以下)を満たしているかの正確な確認が不可欠です。
3.国外に居住する親族の場合
国外に居住する親族(国外居住親族)を扶養に入れる場合は、慎重に進める必要があります。この場合、国内の親族とは異なり、単に申告書に名前を書くだけでは控除が認められません。
年末調整の際に、「親族関係書類」と「送金関係書類」という2種類の証明書類を会社に提出する必要があります。これらの書類によって、従業員がその親族と法的な親族関係にあり、実際に生計を支えるための送金をその年に行っているかを客観的に証明しなければなりません。

【国外扶養】控除適用に必要な3つの書類
国外居住親族に係る扶養控除の適用を受けるには、「親族関係書類」と「送金関係書類」の提出が必須です。これらの書類は、税務署からの求めがあった際に提示するのではなく、年末調整を行う勤務先(会社)が原本を確認して、保管する必要があります。
もし書類が外国語で作成されている場合は、その内容を理解するために「翻訳文」も併せて提出してもらう必要があります。手続きに時間がかかるため、対象となる従業員には早期に準備を依頼する点が肝要です。
1.親族関係書類
「親族関係書類」とは、国外居住親族が、従業員の親族であると証明する書類です。国税庁は、以下のいずれかの書類を例として挙げています。
- 戸籍の附票の写しその他の国または地方公共団体が発行した書類、およびその親族のパスポートの写し
- 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など)
これらの書類は、扶養対象となる親族ごとに必要です。たとえば、配偶者と子どもの2人を扶養に入れる場合は、それぞれについて親族関係を証明する書類が必要となります。
参考:非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ|国税庁
2.送金関係書類
「送金関係書類」とは、従業員がその年に、その国外居住親族の生活費や教育費に充てるために送金を行ったと明らかにする書類です。これは、実際に生計を支えている証拠となります。
具体的には、金融機関が発行した「外国送金依頼書の控」や、クレジットカード会社が発行した「利用明細書」(家族カードの利用分)など、その年に送金した事実が確認できる必要があります。
また、扶養する親族全員に個別に送金する必要はありません。代表者(例:配偶者)への一括送金でも認められます。
3.外国語書類の翻訳文
「親族関係書類」や「送金関係書類」が外国語(英語や中国語、ベトナム語など)で作成されている場合、年末調整を行う会社(日本の担当者)がその内容を正確に把握できないため、日本語の「翻訳文」の添付が必須です。
この翻訳は、公的な機関によるものである必要はなく、従業員本人が翻訳したものでも構いません。しかし、会社側は提出された翻訳文が原文と相違ないかを確認する責任を負います。不備があると控除が認められないリスクがあるため、正確な翻訳が欠かせません。

外国人の年末調整手続きで押さえるべき4つの注意点
外国人の年末調整は、書類の言語の問題だけでなく、在留資格の確認や、前職が海外であった場合の所得の扱いなど、事前に知っておくべき注意点があります。ここでは、外国人の年末調整手続きで押さえるべき注意点を解説します。
1.在留資格とマイナンバーの確認
基本として、その外国人従業員が正規の在留資格を持って就労しているかの確認が必要です。不法就労者を雇用していた場合、年末調整以前に法的な問題となります。
また、日本に中長期在留する「居住者」には、原則としてマイナンバー(個人番号)が発行されます。マイナンバーは、源泉徴収票や扶養控除等申告書への記載が必須です。
入社時にマイナンバーを提出してもらうよう徹底して、まだ取得していない従業員には市区町村の役場で手続きするよう指導しなければなりません。
なお、外国人採用における注意点については、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事:外国人採用における注意点は7つ|採用動向やメリット・デメリット、採用ステップをご紹介!
2.年の途中で入国・出国した場合の扱い
年の途中で入国して、「居住者」となった従業員の場合、年末調整の対象となるのは、居住者となった日以降に支払われた給与のみです。入国前に海外で得ていた所得(母国の会社での給与など)は、日本の年末調整の対象にはなりません。
一方、年の途中で出国して、「非居住者」となった場合も注意が必要です。原則として出国日までに支払われた給与について、年末調整(または確定申告)を行います。出国後の給与は、非居住者としての課税(20.42%の源泉徴収)対象です。
3.社会保険料控除と国民年金・国民健康保険
日本国内で支払った社会保険料(厚生年金保険料や健康保険料、雇用保険料など)は、給与から天引きされている分については、日本人と同様に全額が社会保険料控除の対象です。
また、従業員が、入社前に自分で国民年金保険料や国民健康保険料を支払っていた期間がある場合、支払いを証明する「控除証明書」を提出すれば、その分も合わせて控除できます。しかし、海外で支払った社会保険料に相当するものは、日本の社会保険料控除の対象にはなりません。
なお、外国人労働者の社会保険への加入については、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事:外国人労働者は社会保険への加入が必要?日本における健康保険や労働保険の概要を徹底解説!
4.生命保険料控除・地震保険料控除の対象範囲
生命保険料控除や地震保険料控除も、年末調整における代表的な所得控除です。これらの控除が適用できるケースは限定されます。
日本の保険会社や認可を受けた外国の保険会社等と契約して、日本国内で保険料を支払った場合のみ対象です。従業員が母国で契約して、保険料も海外で支払っている生命保険や地震保険(火災保険)は、日本の年末調整で控除の対象にできません。
従業員が控除証明書を提出してきた際は、契約内容が日本の税制上の要件を満たしているかの確認が必要です。

年末調整の対象外となる2つのケース
外国人の従業員が「居住者」であったとしても、年末調整の対象とならず、従業員自身が確定申告をしなければならないケースがあります。会社側は、どの従業員が年末調整の対象外となるかを把握して、対象者へ適切にアナウンスする責任があります。
1.2カ所以上から給与を受け取っている場合
年末調整は、原則として「主たる給与」を支払っている1社の勤務先でしか行えません。外国人従業員が、副業やアルバイトなどで2カ所以上の会社から給与を受け取っている場合、主たる勤務先以外の給与(従たる給与)は年末調整の対象外です。
従たる給与の収入金額と、給与所得以外の各種所得(不動産所得など)の合計額が年間20万円を超える場合、従業員本人がすべての所得を合算して確定申告を行わなければなりません。
2.医療費控除や寄附金控除などを受ける場合
医療費控除や寄附金控除、1年目の住宅ローン控除(雑損控除も含む)は、年末調整では手続きできません。これらの控除を受けたい従業員は、国籍に関わらず、自身で確定申告を行う必要があります。
日本に来て間もない従業員は、確定申告の制度自体を知らない可能性もあります。会社としては、年末調整で対応できる控除とできない控除の範囲を明確に説明して、該当する従業員には確定申告の案内(申告時期や方法など)を行いましょう。

外国人採用の相談に「グローバルヒューマニー・テック」がおすすめな理由

「株式会社グローバルヒューマニー・テック」は、グローバル人材に対する「総合的な生活支援」を実施している企業です。年末調整を含む外国人材の雇用には専門的な手続きが伴いますが、同社は「豊富な実績による盤石なサポート体制」と「IT技術をかけ合わせた独自のノウハウ」が強みです。
これにより、外国人労働者の支援プラットフォームを充実させ、「外国人材の安心安全な採用支援」から「就業支援」「生活支援」までを一貫してサポートしています。年末調整のような複雑な労務管理も含め、人手不足をグローバルソリューションで解決を使命としており、外国人を雇用するうえでの強力なパートナーとなります。 ⇒株式会社グローバルヒューマニー・テックに相談する

外国人 年末 調整でよくある3つの質問
外国人 年末 調整でよくある質問をご紹介します。それぞれの内容について詳しくみていきましょう。
質問1.年末調整の書類は英語で作成してもよいですか?
年末調整で使用する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や「保険料控除申告書」などの公式な様式は、日本語で記載する必要があります。国税庁は、外国語版の様式を提供していません。
しかし、従業員が日本語の読み書きに不安がある場合、会社がサポートする方法があります。独自に英語やそのほかの言語で記載例や補足説明資料を作成して、配布すると有効です。しかし、提出される申告書本体は、必ず日本語で正しく記入してもらう必要があります。
質問2.国外扶養親族の「送金関係書類」はいくら送金すればよいですか?
国外居住親族への送金について、税法上「最低いくら送金しなければならない」という具体的な金額の基準は設けられていません。従業員がその親族の「生計を支えている」という実態を証明する必要があります。
送金額があまりにも少額(年間で数千円程度)である場合は、注意が必要です。税務調査で「生計を一にしている」とは認められず、扶養控除が否認されるリスクがあります。社会通念上、その国の物価で生活費や教育費の一部を賄える程度の送金実績が求められます。
質問3.租税条約の届出をしている従業員の年末調整は?
従業員の母国と日本との間で「租税条約」が締結されている場合、特定の要件(教師、留学生など)を満たせば、日本での所得税や住民税が免除されるケースがあります。この免税措置を受けるには、事前に「租税条約に関する届出書」を税務署に提出しなければなりません。
この届出書を提出して、所得税の免除を受けている従業員は、日本の所得税が課税されていないため、年末調整の対象にはなりません。しかし、住民税の免除も受ける場合は別途手続きが必要なため、市区町村への確認も必要です。

まとめ
外国人の年末調整を行う際は、対象の従業員が所得税法上で、「非居住者」の場合は年末調整の対象とはなりません。「居住者」に該当する場合、基本的には日本人従業員と同様の手順で進めますが、特有の注意点がいくつか存在します。
母国などに住む「国外居住親族」を扶養に入れる場合、「親族関係書類」と「送金関係書類」の2種類の証明書類が必須です。これらの書類が外国語であれば、日本語の「翻訳文」も併せて提出してもらう必要があります。
また、生命保険料控除が国内契約のものに限られる点や、医療費控除を受けるには別途確定申告が必要な点も注意しましょう。これらの手続きを正確に行うためには、人事・労務担当者が制度の違いを理解して、対象となる従業員へ早めに必要書類をアナウンスしなければなりません。
外国人の年末調整や労務管理は、専門的な知識と対応が求められる複雑な業務です。株式会社グローバルヒューマニー・テックは、外国人労働者の年末調整の手続きはもちろん、採用後の定着支援まで、企業の課題に寄り添ったサポートを提供します。
外国人雇用に関するお悩みや疑問点があれば、まずは一度気軽に問い合わせてください。⇒株式会社グローバルヒューマニー・テックに相談する