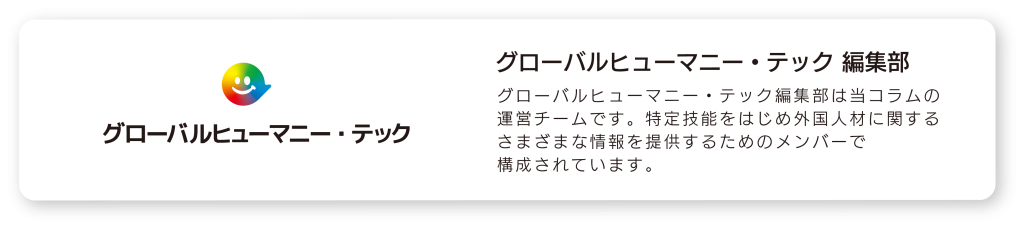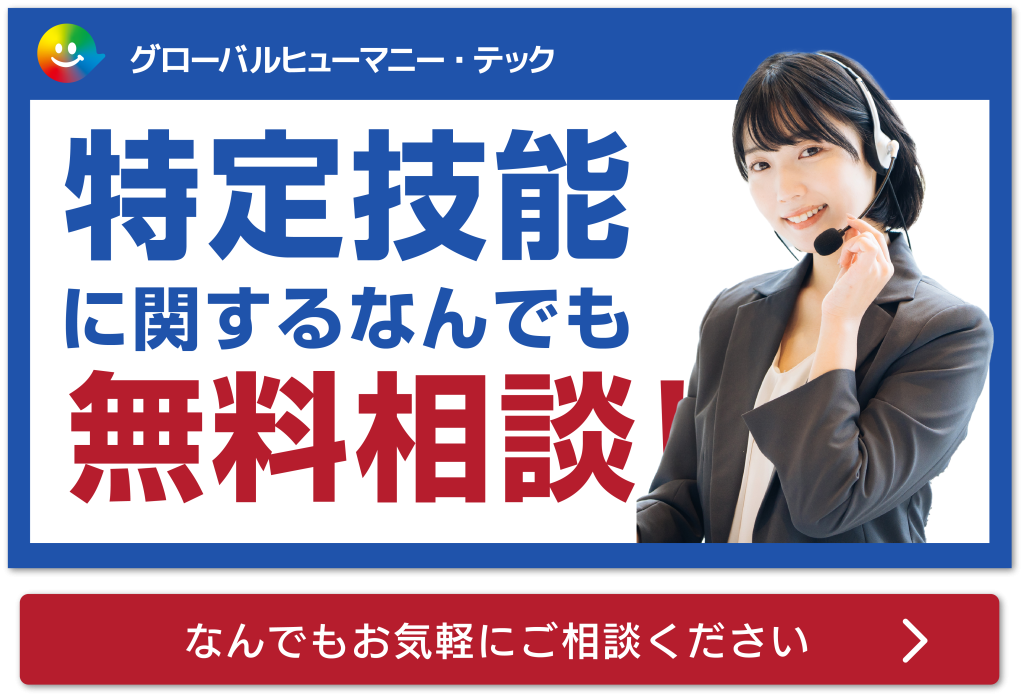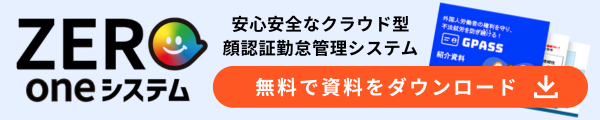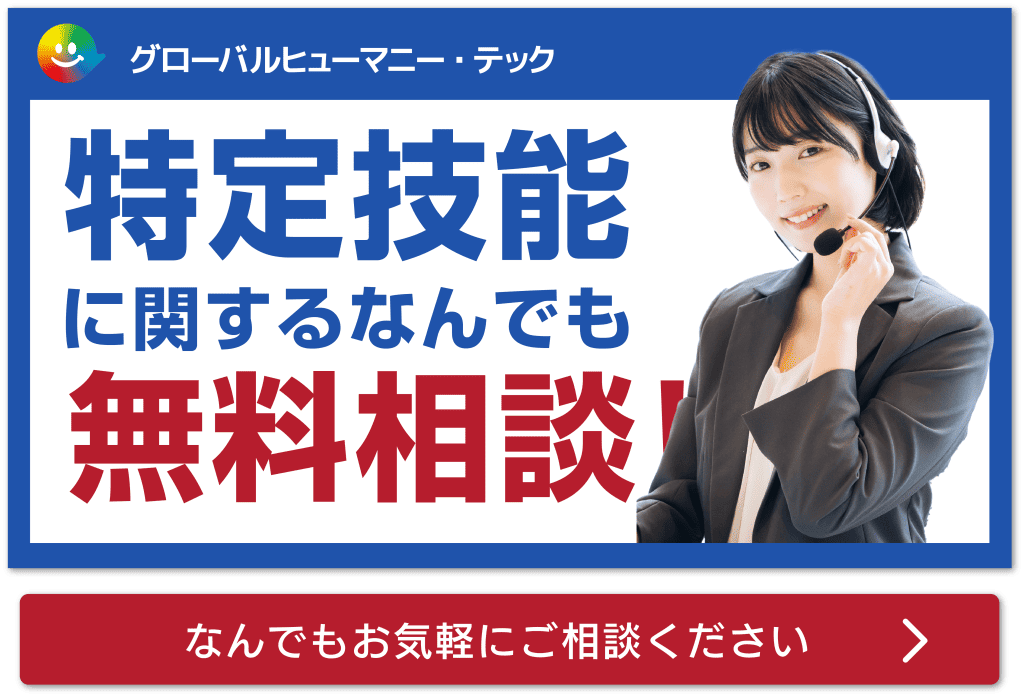近年、外国人労働者の採用は多くの企業にとって大切な経営戦略の1つとなっています。しかし、外国人労働者の税金に関しては、日本人とは異なる特有の制度や複雑なルールがあるため、人事・経理担当者だけでなく、外国人労働者本人にとっても理解が難しいテーマです。
この記事では、外国人労働者の税金に関する基本的な仕組みや企業が知っておくべき注意点を解説します。また、よくある質問をご紹介しますので、外国人労働者が在留資格に影響が出たりするような税務上のトラブルを避けるために、ぜひ参考にしてください。
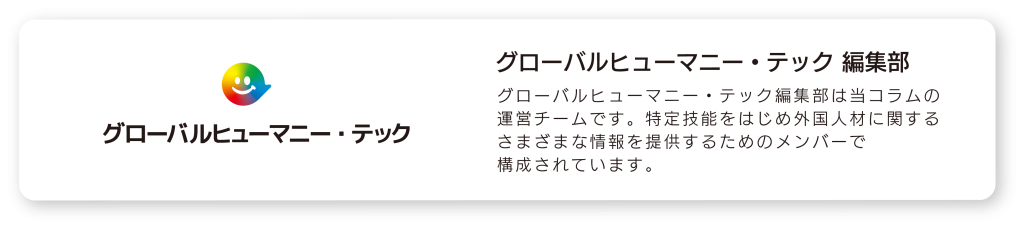
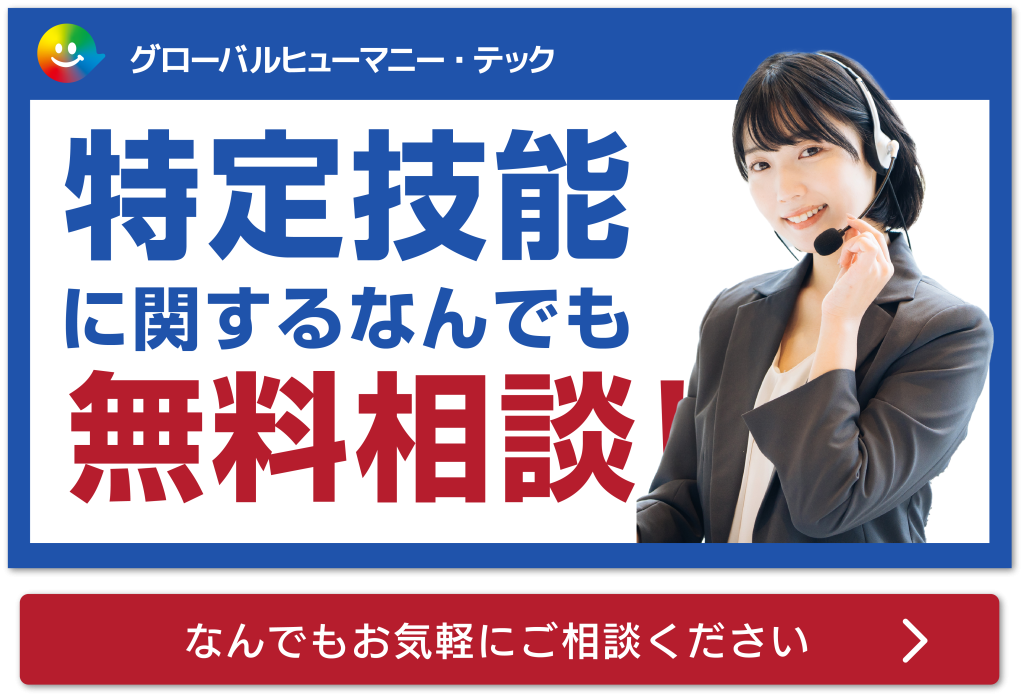
外国人労働者の税金の基本となる3つの区分
外国人労働者が日本で支払うべき税金の仕組みを理解するために基本となる項目が「居住形態」による区分です。この区分によって、所得税や住民税の課税対象となる所得の範囲や税率が大きく変わります。
1.居住者と非居住者の定義
外国人労働者の税金を考えるには、当事者が「居住者」か「非居住者」に該当するのかを判断しなければなりません。この区分は、住所や滞在期間によって決まります。
居住者とは、日本国内に「住所」がある人、または現在まで引き続いて1年以上「居所」がある人です。通常、外国人労働者として1年以上の在留資格で働いている方は、「居住者」に該当します。
一方、非居住者とは、居住者以外の外国人を指しており、短期滞在者が該当します。この居住形態によって、課税される所得の範囲が大きく異なる点が特徴です。
2.居住形態による課税範囲の違い
「居住者」と「非居住者」では、課税対象となる所得の範囲が以下のように明確に異なります。
| 居住形態 | 課税対象となる所得の範囲 | 源泉徴収の税率(給与所得) |
| 居住者 | 全世界の所得(日本国内・国外すべて)が課税対象となる。しかし、非永住者の場合は国外所得のうち日本国内へ送金されたもののみが課税対象 | 日本人同様、累進課税(5%〜45%)が適用され、年末調整や確定申告で精算される |
| 非居住者 | 日本国内で発生した所得(国内源泉所得)のみが課税対象となる | 原則として一律20.42%の税率が適用され、源泉徴収のみで課税関係が完結する。年末調整は原則不要 |
このように、居住者であれば全世界の所得に対して税金がかかりますが、非居住者であれば国内で稼いだ所得のみが対象となる点が違いです。企業側は、採用した外国人労働者の居住形態を正確に把握して、適切な源泉徴収と税金の計算を行いましょう。
3.外国人労働者が支払うべき税金
外国人労働者が日本で働くために支払う必要のある主な税金は、「所得税」と「住民税」の2種類です。詳しくは、以下のとおりです。
- 所得税
個人の年間所得に対して国に納める国税。外国人労働者の場合も、居住形態に応じて課税され、原則として毎月の給与から源泉徴収される
- 住民税
都道府県と市区町村が課税する地方税で、教育・福祉・ゴミ処理などの公共サービスを維持するために使われる。住民税は前年の所得にもとづいて計算され、1月1日時点で日本に住所がある人に課税されるため、日本に来た初年度の外国人労働者は、住民税は課税されない

外国人労働者の税金に関する2つの優遇制度
外国人労働者の税金については、二重課税を防いだり、生活の負担を軽減したりするための優遇制度が設けられています。企業は、これらの制度を理解して、該当する外国人労働者に適切に適用できるようサポートしなければなりません。
1.租税条約による免税・軽減措置
日本は、各国と租税条約を締結しており、外国人労働者の所得に対する二重課税を防止したり、課税の取り扱いを明確にしたりしています。この条約によって、一定の条件を満たす外国人労働者は、所得税の免除や軽減措置を受けられる場合があります。
たとえば、短期滞在者免税制度は、「滞在期間が183日以内であること」などの条件を満たした場合に、日本の所得税が免除される制度です。また、一部の租税条約には、留学生や事業修習者など特定の在留資格を持つ人に対する免税規定が設けられています。
この優遇措置を適用するためには、給与支払日の前日までに「租税条約に関する届出書」を税務署に提出する必要があるため、企業側は外国人労働者への周知と手続きのサポートが不可欠です。
2.国外居住親族に係る扶養控除の厳格化
外国人労働者が母国に住む家族を扶養している場合、一定の条件のもとで扶養控除を受けられます。これは、日本人と同様に所得税を計算するために、節税効果をもたらす優遇制度です。
しかし、2023年(令和5年)からは、国外に居住する扶養親族への扶養控除の適用が厳格化されました。主な変更点として、30歳以上70歳未満の国外居住親族については、留学している者や障害者、または納税者からその年に38万円以上の生活費・教育費の送金を受けている者に限定されました。
扶養控除を申請するためには、「親族関係書類」や「送金関係書類」などの提出が必要です。外国人労働者が適切に手続きできるように、企業は必要書類の確認と収集のサポートを行う必要があります。

外国人労働者の税金処理に関する3つの注意点
外国人労働者の税金処理には、日本人従業員にはない注意点があります。これらのポイントを見落とすと、法令違反や外国人労働者とのトラブルにつながる可能性があるため、企業は、適切な体制を整える必要があります。
1.住民税の特別徴収義務と未納による影響
外国人労働者が居住者に該当する場合、企業は日本人従業員と同様に、住民税の特別徴収義務者となります。これは、毎月の給与から住民税を天引きして、各市区町村に納入する義務です。
住民税は、前年の所得にもとづいて計算されるため、入社2年目以降から課税がはじまります。企業側は、市区町村からの税額通知にもとづき、適切に給与から徴収しなければなりません。
また、住民税の納付を怠ると、企業側が罰則を受ける可能性があるほか、外国人労働者自身の在留期間の更新申請や変更申請が許可されない要因となる場合もあるため、正確な手続きが求められます。
2.退職・帰国時の住民税の一括徴収
外国人労働者が年の途中で退職または帰国(出国)する場合、住民税の未納分について特別な処理が必要です。1月1日〜5月31日までの間に退職・出国する場合は、本人の申出の有無にかかわらず、残りの住民税全額を、最後に支給する給与や退職金から一括徴収して市区町村に納めなければなりません。
6月1日〜12月31日の間に退職・出国する場合は、本人の申し出があれば一括徴収を行えます。一括徴収が行われない場合、残りの住民税は本人が直接納税する普通徴収に切り替わります。
しかし、納税しないまま出国されると回収が困難になるため、企業としては一括徴収を検討して、手続きを支援しましょう。
3.納税管理人の選任と出国時の確定申告
非居住者となる外国人労働者が日本での所得を有したまま出国する場合や、帰国後も日本国内に不動産所得などの所得が生じる可能性がある場合、納税管理人の選任が必要です。納税管理人とは、納税者に代わって税務署からの書類の受領や、納税手続きを代行する人です。
出国する外国人労働者は、出国前に確定申告を行わなければなりません。日本国内に所得が残る場合は、納税管理人を選任して、税務署への届出が義務づけられています。
この手続きを怠ると、外国人労働者本人が納税義務を果たせないだけでなく、企業側の管理体制にも問題が生じる可能性があるため、退職・帰国時には必ず確認し、適切な指導を行いましょう。
参考:No.1923海外勤務と納税管理人の選任又は解任|国税庁

外国人採用の相談に「グローバルヒューマニー・テック」がおすすめ

「株式会社グローバルヒューマニー・テック」は、「グローバル人材に対する総合的な生活支援」をコンセプトに、外国人労働者の採用から就業、生活に至るまでをトータルでサポートする専門商社です。
豊富な実績に裏打ちされた盤石なサポート体制とIT技術をかけ合わせた独自のノウハウにより、外国人労働者の支援プラットフォームを充実させている点が強みです。
外国人材の安心安全な採用支援だけでなく、就業支援や生活支援を通じて、複雑な税金に関する問題を含めた人手不足をグローバルソリューションで解決することをミッションとしています。⇒株式会社グローバルヒューマニー・テックの公式サイトはこちら

外国人労働者の税金でよくある3つの質問
外国人労働者の税金でよくある質問をご紹介します。それぞれの内容について詳しくみていきましょう。
質問1.外国人労働者は日本に来た初年度から住民税を支払う必要がありますか?
住民税は、その年の1月1日時点で日本国内に住所がある人に課税される税金で、前年の所得にもとづいて計算されます。このため、年の途中で来日した外国人労働者の場合、初年度の1月1日時点では日本に住所がないため、住民税は発生しません。
住民税の課税がはじまるのは、日本に来て2年目の6月以降からです。企業は、この住民税の特徴を外国人労働者に明確に伝え、納税に関する認識の齟齬を防ぐ必要があります。
質問2.租税条約の届出を忘れた場合、あとからでも免税・軽減を受けられますか?
租税条約の適用を受けるための「租税条約に関する届出書」は、原則として給与の支払いを受ける日の前日までに、源泉徴収義務者(企業)を経由して税務署に提出しなければなりません。
提出を忘れた場合でも、給与の支払いを受けた日から5年以内であれば、「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書」を税務署に提出すれば、納めすぎた所得税の還付を受けられます。しかし、手続きが煩雑になるため、できる限り事前の届出を徹底しましょう。
質問3.住民税を滞納すると外国人労働者の在留資格に影響が出ますか?
住民税の支払いは、外国人労働者の在留資格の更新に影響する可能性があるため、大きな問題です。住民税の納付状況は、在留期間の更新や変更の審査において、納税義務の履行状況を示す項目として入管庁が確認する大切な要素の1つです。
過去に住民税の未納や滞納がある場合、納税義務を果たしていないと判断され、在留資格の更新申請が不許可になるリスクが高まります。企業側は、住民税が課税され始める2年目以降、特別徴収(給与天引き)を確実に実施するなど、外国人労働者が滞納とならないよう徹底した管理とサポートを行いましょう。

まとめ
外国人労働者の税金は、「居住者」か「非居住者」かによって課税範囲や税率が大きく変わるため、その区分を正しく判断しなければなりません。主要な税金は所得税と住民税であり、所得税には租税条約による免税・軽減措置の可能性があり、扶養控除のルールも2023年から厳格化されています。
住民税の特別徴収義務や、退職・帰国時の一括徴収、納税管理人の選任は、企業が法令を遵守して、労働者のスムーズな帰国を支援するために欠かせない手続きです。複雑な税務処理を適切に行い、外国人労働者が安心して働ける環境の提供は、企業の社会的責任であり、外国人労働者の定着にも直結します。
「株式会社グローバルヒューマニー・テック」は、グローバル人材の受け入れにおいて、豊富な実績とIT技術をかけ合わせた独自のノウハウを持っています。外国人労働者の税金に関する問題を含め、総合的な生活支援を通じてグローバル化をサポートします。
採用後の定着や生活の安心感にお悩みであれば、専門的な支援体制を持つ同社への相談を検討してみてはいかがでしょうか。⇒株式会社グローバルヒューマニー・テックに相談する