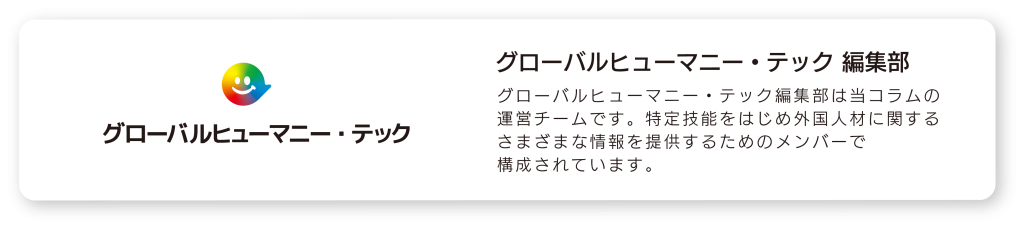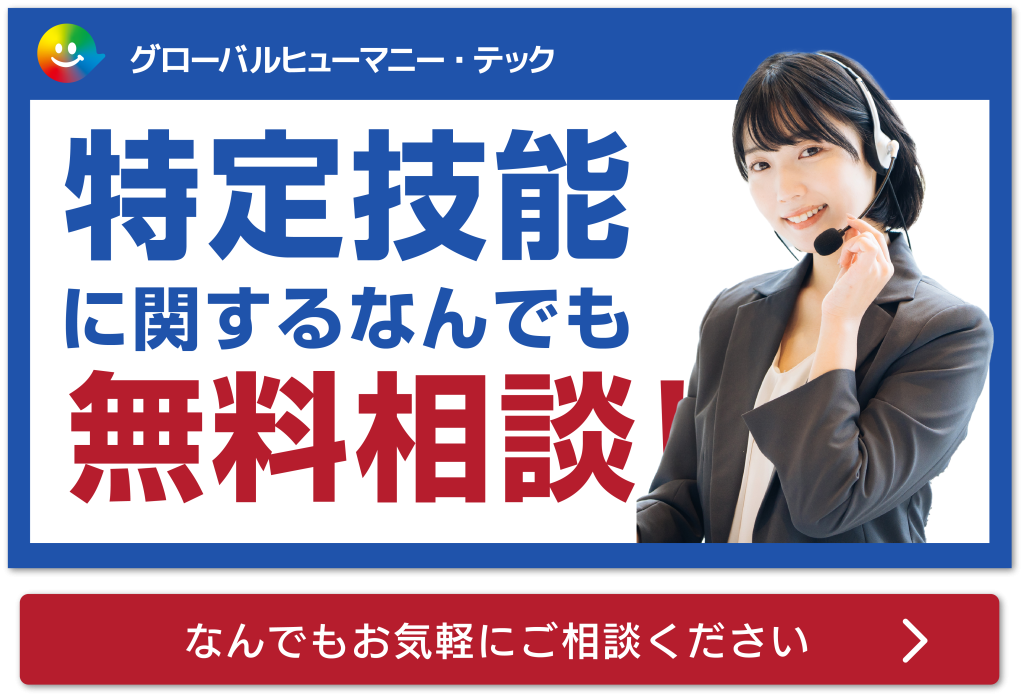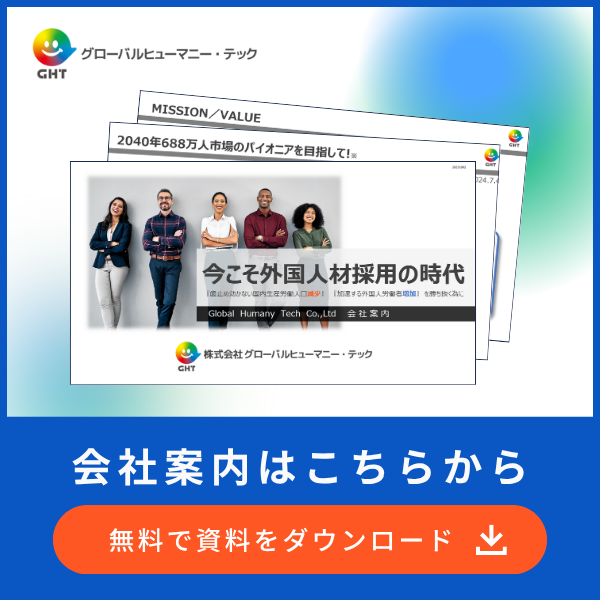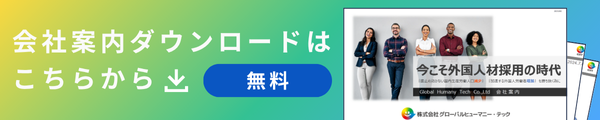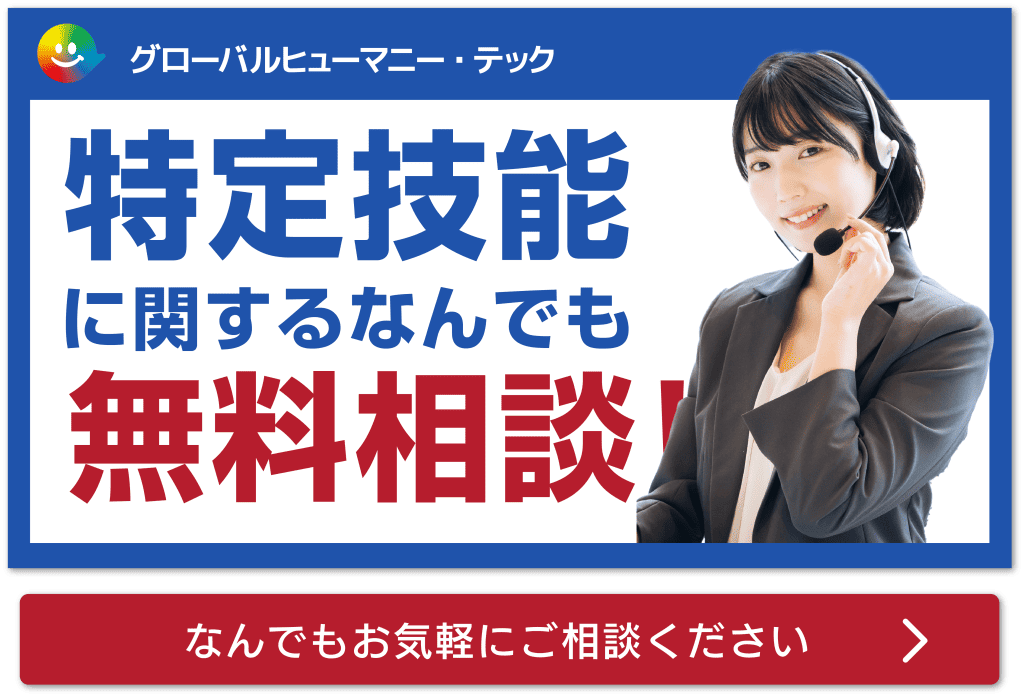日本の農業は、人手不足という深刻な課題に直面しています。高齢化や若年層の農業離れが進む中、農業従事者の確保が難しくなり、農家の運営に大きな影響を及ぼしている状況です。
本記事では、農家における人手不足の現状や主な原因、解決策について解説しています。また、採用できる外国人の種類やよくある質問も紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
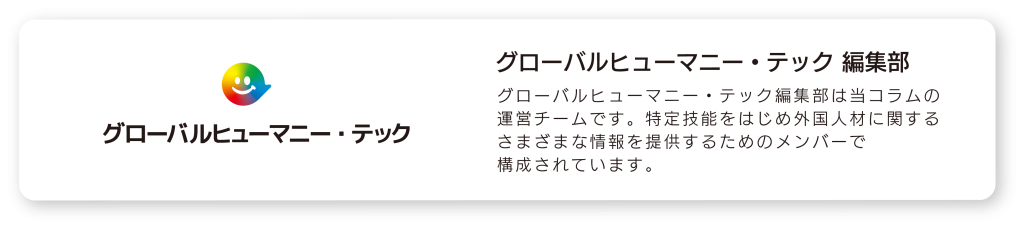
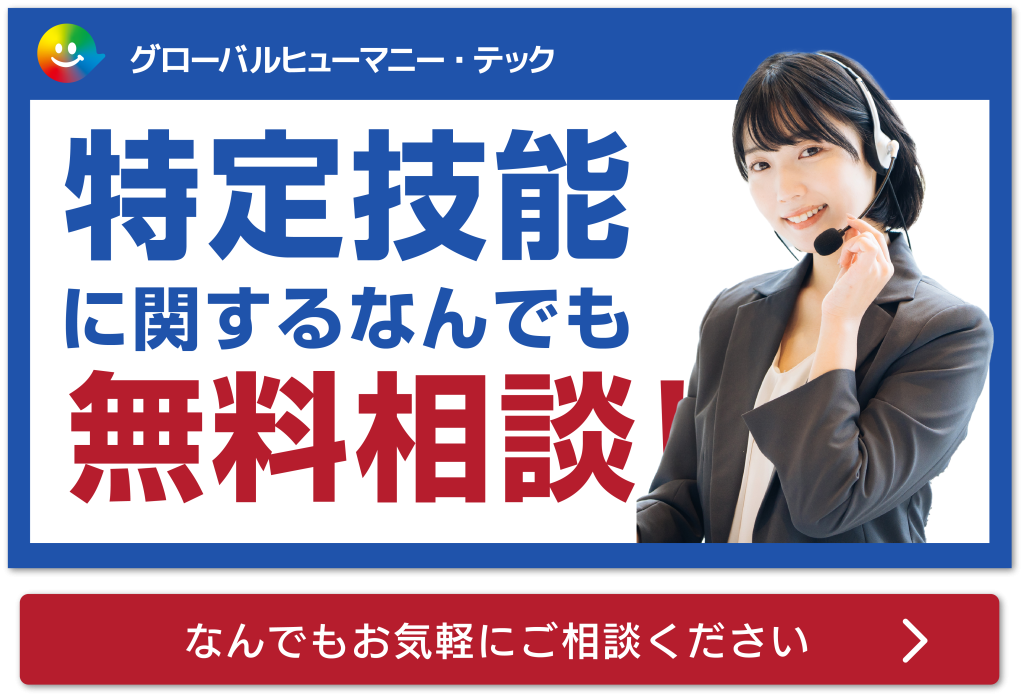
農家における人手不足の現状とは?
日本の農業は、現在、労働力不足という重大な課題に直面しています。この問題の深刻さは、農林水産省が公表したデータからも明らかです。
【基幹的農業従事者(個人経営体)】※単位:万人、歳
| 28年 | 29年 | 30年 | 31年 | 令和2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
| 基幹的農業従事者 | 158.6 | 150.7 | 145.1 | 140.4 | 136.3 | 130.2 | 122.6 | 116.4 |
| うち女性 | 65.6 | 61.9 | 58.6 | 56.2 | 54.1 | 51.2 | 48.0 | 45.2 |
| うち65歳以上 | 103.1 | 100.1 | 98.7 | 97.9 | 94.9 | 90.5 | 86.0 | 82.3 |
| 平均年齢 | 66.8 | 66.6 | 66.6 | 66.8 | 67.8 | 67.9 | 68.4 | 68.7 |
参考:農林水産省 「農業労働力に関する統計」基幹的農業労働者(個人経営体)
特に、農業に従事する中心的な労働者層が減少傾向にある一方で、平均年齢が上昇している現状は、農業の持続可能性に大きな影響を及ぼす可能性があります。このままでは、個人経営の農家が抱える負担が増し、地域農業の生産力や競争力が低下することが懸念されます。
農業の未来を支えるためには、新たな労働力の確保や効率化を図る施策が急務です。

農家が人手不足に陥る主な原因は5つ
次に、農家が人手不足に陥る主な原因について解説します。
- 農業従事者が居住している地方の人口が少ない
- 後継者が見つからない
- 繁忙期と閑散期の差が大きい
- 新規就農のハードルが高い
- 労働環境が良くない
それぞれの内容について詳しくみていきましょう。
1.農業従事者が居住している地方の人口が少ない
日本では、人口減少や高齢化の影響が地方において顕著であり、それが農業分野の人手不足を加速させています。地方の農業従事者は、働き盛りの若年層の減少により、新しい労働力の確保が難しいのが現状です。
さらに、都市部でも人手不足が深刻化している中で、地方における農業は他の職種との競争に直面し、必要な人材を確保するのが困難です。このような背景から、農業地域の人口減少がもたらす影響は、地域社会全体の活力低下につながりかねません。
2.後継者が見つからない
1970年代から指摘されてきた農業の高齢化問題は、今ではさらに加速し、高齢というより老齢と表現される段階に達しています。最大の要因として後継者不足が挙げられ、多くの農家では70歳以上の農業従事者が中心となり、全体の7割が農作業を一人で切り盛りしている状況だとされています。
後継者の不在により作業の手伝いを得るのが難しいため、農作業中の事故も増加傾向にあり、農業現場の労働力の確保と安全対策が急務です。
3.繁忙期と閑散期の差が大きい
農業分野での人手不足の一因として、仕事の季節性が挙げられます。農業は繁忙期と閑散期が明確に分かれており、収穫期など特定の時期には多くの労働力が必要になる一方で、閑散期には仕事が大幅に減少するのが現状です。
この変動のため、安定した収入を求める人々にとって農業は魅力的な職種と感じにくい傾向があります。また、農作業には専門知識や技術が求められる場面も多く、短期雇用者だけで十分に補うことが難しい課題も存在しています。
そのため、農業に携わる人材が持続的に働ける環境を整え、年間を通じて安定した労働機会を提供する仕組みが必要です。こうした取り組みは、農業の労働力不足を解消し、分野の発展にもつながると考えられます。
4.新規就農のハードルが高い
農業における新規就農者の増加を阻む要因として、季節労働の性質が挙げられます。繁忙期にだけ人材が求められるため、年間を通して安定的に働きたいと考える人々にとって、農業は魅力的な選択肢になりにくい状況です。
多くの場合、アルバイトなどの短期雇用が中心となり、農業を職業として選択したい新規就農希望者が定職を得る機会が限られているのが現状です。その結果、農業分野での労働者の高齢化が進行し、分野全体の活力低下を招いています。
こうした課題を解決するためには、通年雇用の仕組みや安定した収入を提供できる環境整備が必要であり、それが農業の未来を支える鍵になると考えられています。
5.労働環境が良くない
農業従事者が減少する背景には、労働環境の課題が大きく影響しています。多くの業種では、勤務条件や休暇制度が明確に整備されていますが、農業ではこれが不十分な場合が多いです。
特に、外作業が主体となる農業では、高温や寒冷といった厳しい気候条件下での労働が求められます。また、労働基準法の適用外となる部分が多く、休憩や労働時間の管理が曖昧になりやすい点も問題です。
こうした状況は、就農を希望する人にとってのハードルとなり、さらには長期的な従事を妨げる要因にもなっています。農業を持続可能な産業とするためには、労働条件の明確化や改善に向けた取り組みが急務です。

農家における人手不足の解決策は5つ
次に、農家における人手不足の解決策をご紹介します。
- 農地面積を特定の地域に集約する
- 最先端のテクノロジーを導入する
- 法人として農業に参入する
- 労働環境を改善する
- 外国人雇用により採用人材の幅を広げる
それぞれの内容について詳しくみていきましょう。
1.農地面積を特定の地域に集約する
農業の効率化を図るためには、分散している農地を集約し、大規模な経営体制の構築が有効です。この取り組みの一環として、農地中間管理機構が全国で活動を展開しています。
この機構は、地域内に点在する農地を一括して借り受け、それを担い手農家に再配分し、農地の有効活用を促進しています。これにより、耕作放棄地の再活用が進むだけでなく、農業機械の導入が容易になるため、連続した作業も可能です。
こうした農地集約化の取り組みは、農業の生産性向上と持続可能性の向上に寄与すると期待されています。
2.最先端のテクノロジーを導入する
スマート農業の進展は、人手不足問題の解決に大きな役割を果たしています。農作業の効率化や従来の作業量の大幅な削減が可能なのは、ロボット技術やICTの活用です。
スマートフォンやアプリを通じて農地の管理や作業記録を自動化すると、作業効率を向上させると同時に、新規就農者でも品質を維持しやすくなります。また、ドローンやAI技術を活用した生育データや気象データの解析により、作物の最適な育成や病害虫の予防が実現可能です。
これにより、従来の労働集約的なモデルから高度な技術を基盤とした農業経営へと転換が進み、持続可能な農業の実現が期待されています。
3.法人として農業に参入する
人材確保や事業の安定性に寄与するのが農業の法人化です。農林水産省の示すように、法人化により経営管理能力や信用力が向上し、経営の発展性が広がるだけでなく、従業員の福利厚生の充実や経営継承の円滑化も期待されています。
この仕組みは、農業に対する信頼性を高め、求職者にとって「安定した職場」として認識される要因となります。さらに、明確な経営方針や福利厚生制度は、新規就農者が農業を選ぶきっかけにもなります。
4.労働環境を改善する
就農者を増やすためには、労働環境の見直しと改善が必要です。農業特有の柔軟性を活かしつつも、労働条件に関しては明確化が求められます。
たとえば、給与形態や年間の作業スケジュールを明示すると、求職者に安心感を与えられます。また、トイレや休憩所、更衣室の整備といった基本的な衛生環境の向上も不可欠です。
さらに、有給休暇の付与や適切な休息時間の確保など、一般的な雇用基準を農業にも適用すれば、働きやすい職場づくりが可能になります。このような取り組みは、農業の魅力を高め、人材不足解消に向けた効果的な手段です。
5.外国人雇用により採用人材の幅を広げる
人手不足の解消策として、外国人材の活用が注目されています。特に地方においては、日本人よりも採用が比較的容易であるという特徴があり、若い労働力として期待が寄せられています。
2023年10月末時点の厚生労働省の調査では、農業分野で働く外国人労働者の割合は2.5%であり、すでに多くの農業法人が外国人技能実習生を積極的に受け入れている状況です。また、2022年版農業法人白書によると、25.5%の企業が技能実習生を受け入れており、その中には6名以上を受け入れる企業も多く存在します。
今後、技能実習制度から育成就労制度への移行が進む中で、どのような外国人材が農業分野で活躍できるかが一層注目されています。
参考:「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和5年10月末時点)|厚生労働省

農家が採用できる外国人の種類は3種類
次に、農家が採用できる外国人の種類について解説します。
- 技能実習生
- 特定技能「農業」
- 在留資格「留学」
それぞれの内容について詳しくみていきましょう。
技能実習生
技能実習生制度は、外国人が日本で技術や知識を習得し、母国での発展に役立てるのを目的としています。実習生は「1号」「2号」「3号」の3つの在留資格に分かれ、それぞれの段階で試験をクリアしながら最大5年間、日本で実習を行う仕組みです。
農業分野では、技能実習生が収穫作業など特定の業務に従事できるため、人手不足を補う貴重な存在となっています。一方、特定技能「農業」では、より幅広い作業が可能であり、技能実習「2号」から資格変更を行うと、さらなる活躍が期待できます。
この制度の活用により、農業分野における多様な労働力の確保と業務効率の向上が可能です。
特定技能「農業」
特定技能「農業」は、日本の農業分野で外国人材が働けるようにする在留資格で、2019年に導入されました。この資格は、耕種農業と畜産農業の2分野に分かれ、それぞれ専用の試験に合格すると業務に従事できます。
特定技能「農業」の大きな特徴は、学歴や母国での職歴が問われないため、資格取得のハードルが比較的低い点です。また、技能実習と比較して、特定技能「農業」では作業範囲が広く、収穫作業に加えて肥料や農薬の散布なども可能です。
この柔軟性は、日本の農業現場における即戦力となり、特に人手不足が深刻な地域で重宝されています。
なお、特定技能と技能実習の違いについては、こちらの記事で詳しく紹介しています。
関連記事:【2024年最新版】特定技能と技能実習の違いは10項目|それぞれに向く企業の特徴も徹底解説! – 株式会社 グローバルヒューマニー・テック
在留資格「留学」
在留資格「留学」を持つ外国人は、条件を満たせばアルバイトとして働けます。この資格は日本の大学や専門学校などでの学業を目的として発行されるもので、働くためには「資格外活動許可」を取得が必要です。
この許可を得ると、報酬を伴う活動が一定の範囲で認められますが、労働時間は週28時間以内に制限されているため、注意が必要です。農業分野においても、耕種や畜産の業務に従事できます。
一方で、日本人の配偶者や永住者など「地位や身分に基づく在留資格」を持つ外国人は、働く時間や内容に制限がなく、日本人と同等の条件で就労できます。これらの制度は、農業分野での労働力確保にも貢献しています。

農家人手不足でよくある3つの質問
最後に、農家人手不足に関してよくある質問をご紹介します。
- 農家における外国人技能実習生の受入状況は?
- 農家が外国人労働者を活用するメリットは?
- 特定技能「農業」は派遣の受け入れもできる?
それぞれの内容について詳しくみていきましょう。
質問1.農家における外国人技能実習生の受入状況は?
外国人技能実習制度は、開発途上国の人材育成を支援し、経済の発展を目的とした取り組みです。この制度により、技能実習生は日本で技術や知識を学び、母国に帰国後、それらを活かして発展に寄与する役割が期待されています。
令和3年度の外国人技能実習機構の調査によると、建設関係が全体の20.8%、食品製造関係が19.5%、機械・金属関係が14.9%と多くの割合を占めています。一方で、農業関係の割合は9.6%に留まり、他分野に比べて低い傾向です。
農業の労働力不足を解消するためには、技能実習制度を通じて農業の魅力をさらに伝え、実習生が農業分野に興味を持つ取り組みが必要です。
質問2.農家が外国人労働者を活用するメリットは?
外国人労働者の導入は、日本の農業分野にさまざまなメリットをもたらします。まず、労働力不足の解消が最大のメリットです。
特に繁忙期には、外国人労働者が人手不足を補い、農作業の停滞を防げるため、生産性が向上します。また、日本の農業において新しい技術や発想を生み出すのは、異なる国や地域での農業経験を持つ彼らです。
たとえば、独自の栽培方法や農作物管理の手法が日本の農業に革新をもたらす可能性が期待できます。さらに、多様な文化背景を持つ外国人労働者が共に働くのは、多文化共生を推進する重要な要素です。
これにより、地域社会が活性化し、新たなコミュニティが形成され、農業だけでなく地域全体に良い影響をもたらします。
なお、外国人労働者を受け入れるメリットについては、こちらの記事で詳しく紹介しています。
関連記事:外国人労働者を受け入れるメリットは5つ|採用の注意点やステップを詳しく解説します! – 株式会社 グローバルヒューマニー・テック
質問3.特定技能「農業」は派遣の受け入れもできる?
特定技能「農業」は、派遣雇用が可能な点が特徴的です。この資格で派遣が認められている理由の一つは、農業の仕事が季節や地域に大きく依存し、労働需要が変動するためです。
繁忙期に多くの労働力を必要とする農家にとって、派遣を活用すれば効率的に人手不足を補える仕組みとなっています。この柔軟な雇用形態により、農業の現場では必要なタイミングで適切な労働力の確保が可能になります。
また、派遣雇用の利用は、農業経営の効率化にもつながり、特に小規模農家や短期間の労働力を求める場合に大きなメリットです。

まとめ
本記事では、農業分野で深刻化する人手不足の現状とその原因、さらに解決策について解説しました。
高齢化が進む一方で、後継者が不足しており、多くの農家が労働力の確保に苦戦しています。これに対し、外国人労働者の活用が広がり、技能実習生や特定技能「農業」を取得した人々が日本の農業を支える大きな力となっています。
これらの人材は、農業の労働力を補うだけでなく、新たな技術やアイデアをもたらす可能性を秘めています。しかし、持続可能な発展のためには、彼らが働きやすい環境を整え、労働条件の向上や業務の効率化を進めなくてはなりません。
農業現場の改善は、長期的な労働力不足の解消に寄与すると考えられます。日本の農業が直面する課題を乗り越えるためには、多様な人材を受け入れつつ、現場の課題を解決していく取り組みが不可欠です。
なお、株式会社グローバルヒューマニー・テックでは、グローバル人材に対する総合的な生活支援を実施しており、外国人の受け入れにおける豊富な経験と知識を有しています。ご相談・お見積りはもちろん無料です。まずはお気軽にお問合せください。⇒株式会社グローバルヒューマニー・テックに相談する