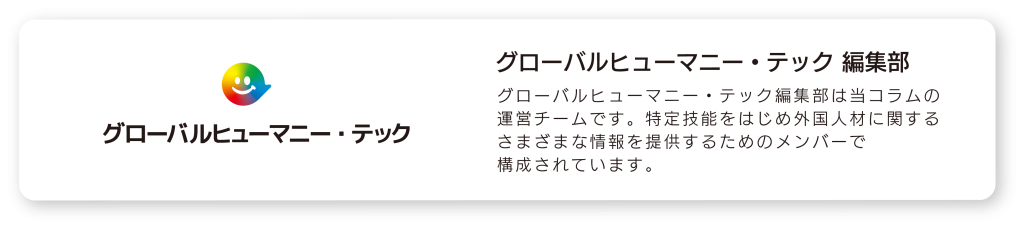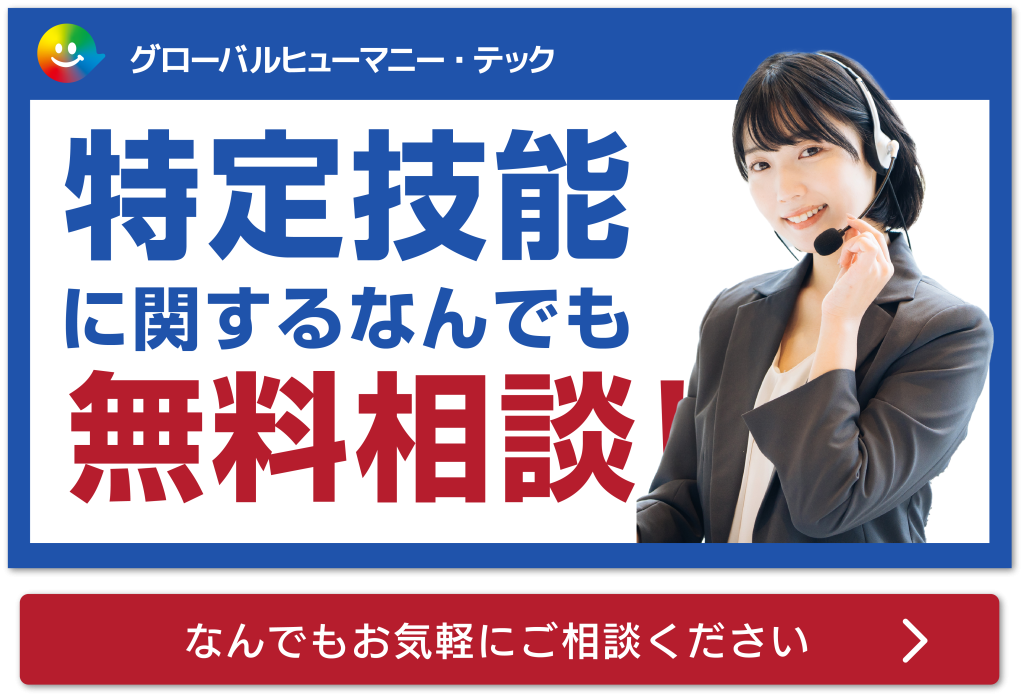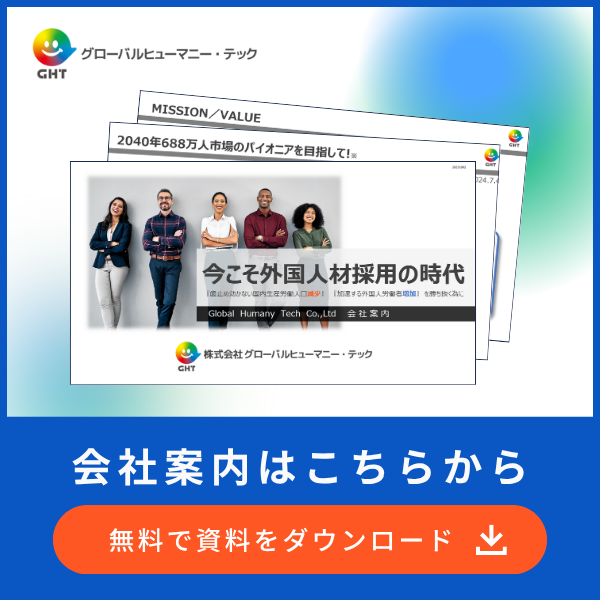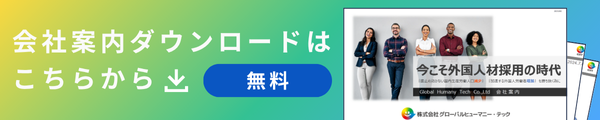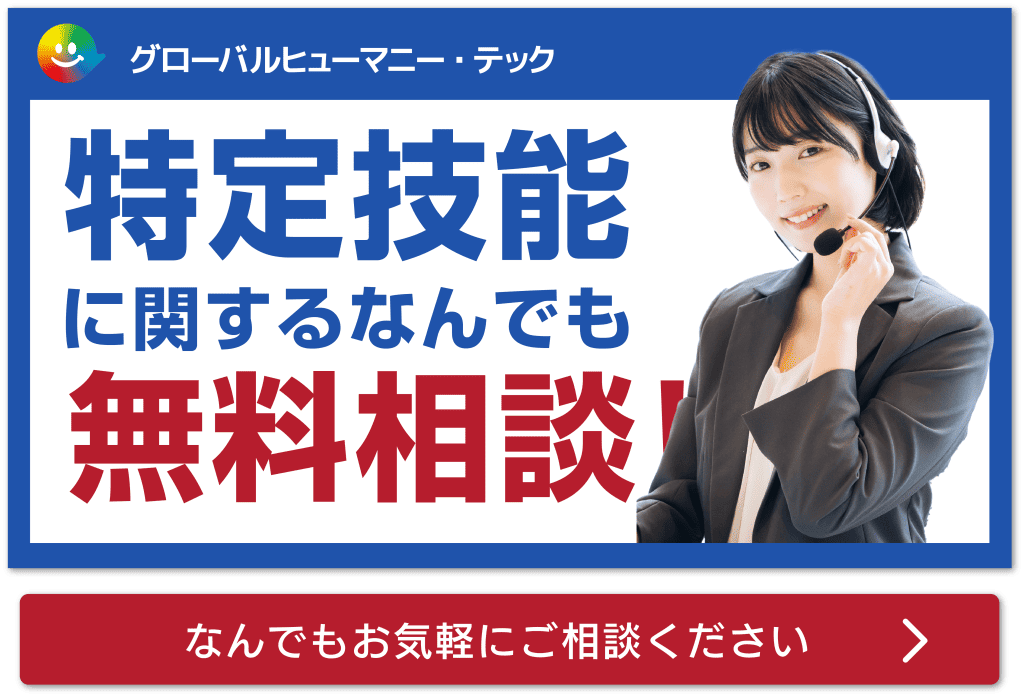日本で生活する外国人にとって、在留カードは身分を証明する大切なものです。しかし、有効期限が切れてしまうと、日本に滞在し続けられなくなり、罰則の対象となる可能性もあります。
本記事では、在留カードの有効期限の種類や更新手続き、有効期限切れのリスクをご紹介します。また、よくある質問も解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
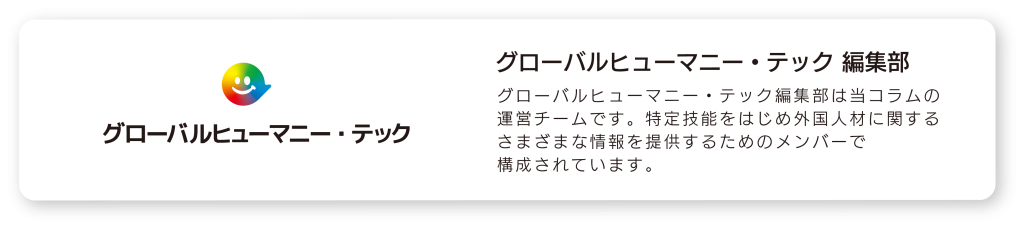
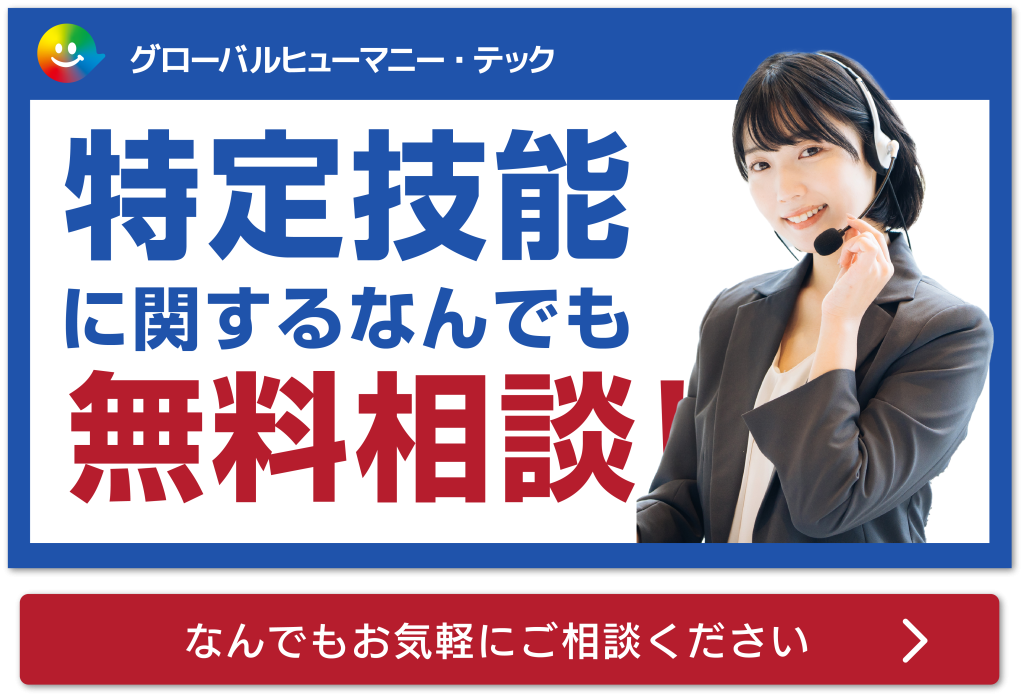
在留カードの有効期限は2種類
まずは、在留カードの2種類の有効期限について解説します。それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
1.在留期間の満了日
在留カードの表面に記載されている「在留期間(満了日)/ PERIOD OF STAY(DATE OF EXPIRATION))」は、その在留資格で日本に滞在できる期限です。たとえば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で「3年」の在留期間が許可されている場合、その満了日までに在留期間の更新申請を行わなければなりません。
この期限を1日でも過ぎてしまうと、原則として不法滞在(オーバーステイ)となってしまうため、注意が必要です。この期限を基点に、更新のスケジュールを立てましょう。
なお、就労ビザの有効期限については、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事:就労ビザの有効期間(在留期間)とは?有効期間の決まり方や更新にかかる期間を徹底解説!
2.在留カードの有効期間
在留カード自体にも有効期間は、「永住者」や「高度専門職2号」の資格を持つ方に関係します。これらの在留資格には、在留期間の定めがありませんが、在留カードは身分証明書としての正確性を保つため、定期的な更新が必要です。
具体的には、16歳以上の方の場合、在留カードの有効期間は交付日から7年間と定められています。この有効期間は、カードの一番下に記載されているため、注意が必要です。また、永住者の方でも、カード自体の更新を怠ると罰則の対象となるため、忘れずに手続きを行いましょう。

在留カードの更新は5つのステップ
次は、在留カードの更新の流れについて解説します。それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
1.申請期間の確認
一般的な在留資格(永住者・高度専門職2号以外)の場合、在留期間が満了する3か月前から申請が可能です。一方、「永住者」や「高度専門職2号」の資格を持つ方は、在留カードの有効期間が満了する2か月前から申請できます。
申請期間に入ったら、すみやかに準備をはじめましょう。書類の準備には時間がかかる場合もあるため、余裕を持ったスケジュールを立てておくと安心です。
なお、在留カードの更新はいつからできるかについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事:在留カードの更新はいつからできる?更新の方法や期限が切れた場合の対象方法を徹底解説!
2.必要書類の準備
必要書類は、現在の在留資格や個人の状況によって異なります。共通して必要となるのは、以下の書類です。
- 在留期間更新許可申請書
- 証明写真
- パスポート
- 現在の在留カード
たとえば、就労ビザの方であれば会社の在職証明書や住民税の課税・納税証明書、配偶者ビザの方は、配偶者の戸籍謄本や身元保証書などが必要です。必要な書類の詳細は、必ず出入国在留管理庁のウェブサイトで最新の情報を確認してください。
書類に不備があると、申請が受理されなかったり、審査に時間がかかったりする原因となります。
3.申請場所での手続き
居住している地域を管轄する地方出入国在留管理庁へ申請に行きます。申請は、原則として本人が行う必要がありますが、法定代理人や、届出を行った行政書士が代理で申請が可能です。
窓口は混雑する場合が多いため、時間に余裕を持って行きましょう。また、申請書が受理されると、在留カードの裏面に「在留期間更新許可申請中」のスタンプが押されます。
このスタンプがあれば、万が一審査中に在留期限を過ぎてしまっても、特例として満了日から2か月間は適法に日本に滞在し続けられます。
4.審査結果の通知
審査期間は通常2週間から1か月程度ですが、申請内容や時期によってはそれ以上かかる場合もあります。審査が完了して、無事に許可されると、入管からハガキ(通知書)が郵送で届きます。
このハガキには、新しい在留カードの受け取りに必要な事項が記載されています。不許可の場合は、その旨の通知が届きます。許可の通知が届くまで不安になりますが、申請中のスタンプが押してあれば合法的に滞在できるため、焦らずに結果を待ちましょう。
5.新しい在留カードの受領
許可のハガキが届いたら、指定された期間内に再度入管へ行き、新しい在留カードを受け取ります。受け取りの際には、以下の書類が必要です。
- 届いたハガキ
- パスポート
- 現在持っている在留カード
- 手数料4,000円分の収入印紙
収入印紙は、入管内の売店や郵便局で購入できます。窓口でこれらの書類を提出して、新しい在留カードが交付されたら、記載内容(氏名、在留資格、新しい在留期間満了日など)に誤りがないかをその場で必ず確認してください。

在留カードの有効期限切れのリスク
次は、在留カードの有効期限切れのリスクについて解説します。それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
1.不法滞在(オーバーステイ)の発生
在留期間の満了日を1日でも過ぎてしまうと、その瞬間から「不法滞在(オーバーステイ)」です。これは、出入国管理及び難民認定法に違反する状態であり、日本に滞在する法的な根拠を失います。
オーバーステイになると、現在就いている仕事で働き続けられず、アルバイトをすることも一切できなくなります。さらに、国民健康保険の資格を失い、病気や怪我をしても医療費が全額自己負担になるなど、日常生活に深刻な影響がおよびます。
なお、オーバーステイの罰則については、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事:オーバーステイの罰則とは?オーバーステイの外国人雇用を防ぐためのポイントもご紹介!
2.罰則と退去強制の可能性
不法滞在(オーバーステイ)の状態が続くと、入管法にもとづき「3年以下の懲役もしくは禁錮または300万円以下の罰金」が科される可能性があります。さらに、重い処分として「退去強制」いわゆる強制送還の対象となります。
一度退去強制になると、原則として5年間(場合によっては10年間)は日本に再入国できません。また、永住者の方であっても、在留カードの更新を怠った場合は「1年以下の懲役または20万円以下の罰金」の対象となるため、注意が必要です。

外国人採用の相談に「グローバルヒューマニー・テック」がおすすめな理由
株式会社グローバルヒューマニー・テックでは、グローバル人材に対する総合的な生活支援を実施しています。豊富な実績による盤石なサポート体制とIT技術をかけ合わせた独自のノウハウで、外国人労働者の支援プラットフォームを充実させています。
外国人材の安心安全な採用支援はもちろん、就業支援や生活支援を通じて人手不足をグローバルソリューションで解決するのが私たちの使命です。⇒株式会社グローバルヒューマニー・テックに相談する

在留カード 有効期限でよくある3つの質問
次は、在留カード 有効期限でよくある質問について解説します。それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
質問1.在留期間の更新申請中に期限が切れても大丈夫ですか?
在留期間の満了日までに更新申請が受理されていれば、「在留期間の特例」が適用されます。これにより、元の在留期間が満了した後も、審査結果が出るまで、または満了日から最大2か月間は、適法に日本に滞在し続けられます。
申請が受理された際に、在留カードの裏面に押される「在留期間更新許可申請中」のスタンプが証明となるため、焦る必要はありません。
質問2.在留期間の更新が不許可になるのは、どのような場合ですか?
在留期間の更新は自動的に許可されるわけではなく、いくつかの理由で不許可となる場合があります。多い理由として、住民税や年金、健康保険料などの公的義務を怠っているケースです。
また、日本での素行も審査対象となり、交通違反を含む法律違反や、住所変更の届け出を怠るなどの入管法上の義務違反も、不許可の原因となり得ます。
さらに、現在の在留資格で認められている活動を実質的に行っていない場合や、日本で安定して生活できるだけの収入や資産がないと判断された場合も、更新が認められない可能性があります。日頃から納税や各種届出などの義務を誠実に果たして、法律を遵守しましょう。
質問3.1日だけ有効期限を過ぎてしまったら、更新はできませんか?
病気や天災など、本人に責任がないやむを得ない理由があった場合は、特別に申請が受理される可能性もあります。しかし、「うっかり忘れていた」という理由は通常認められません。
期限を過ぎてしまった場合は、できるだけ早く自ら地方出入国在留管理庁に出頭して、誠実に事情を説明してください。対応が遅れるほど状況は悪化するため、正直に状況を話して、指示を仰ぎましょう。

まとめ
この記事では、在留カードの有効期限についてや、具体的な更新手続きのステップ、有効期限切れのリスクを詳しく解説しました。
在留カードの有効期限管理は、日本で安定した生活を送るための基礎であり、大切な義務の1つです。うっかり期限を過ぎてオーバーステイの状態になれば、仕事を失い、退去強制になるという深刻な事態も起こり得ます。
このようなリスクを確実に避けるため、在留カードの満了日を再確認し、3か月前を目安に余裕を持って準備をはじめましょう。計画的に更新申請を進めるようにしてください。
なお、株式会社グローバルヒューマニー・テックでは、グローバル人材に対する総合的な生活支援を実施しており、外国人の受け入れにおける豊富な経験と知識を有しています。ご相談・お見積りはもちろん無料です。まずはお気軽にお問合せください。⇒株式会社グローバルヒューマニー・テックに相談する