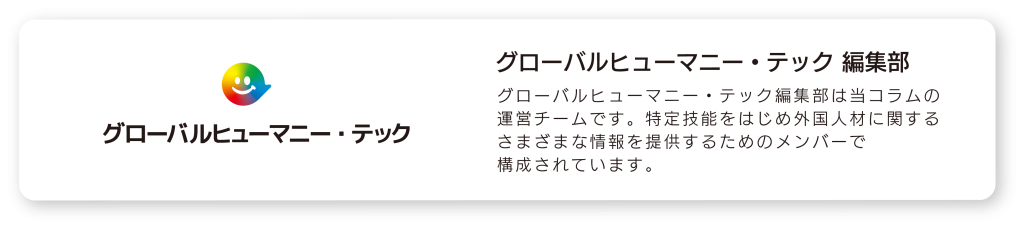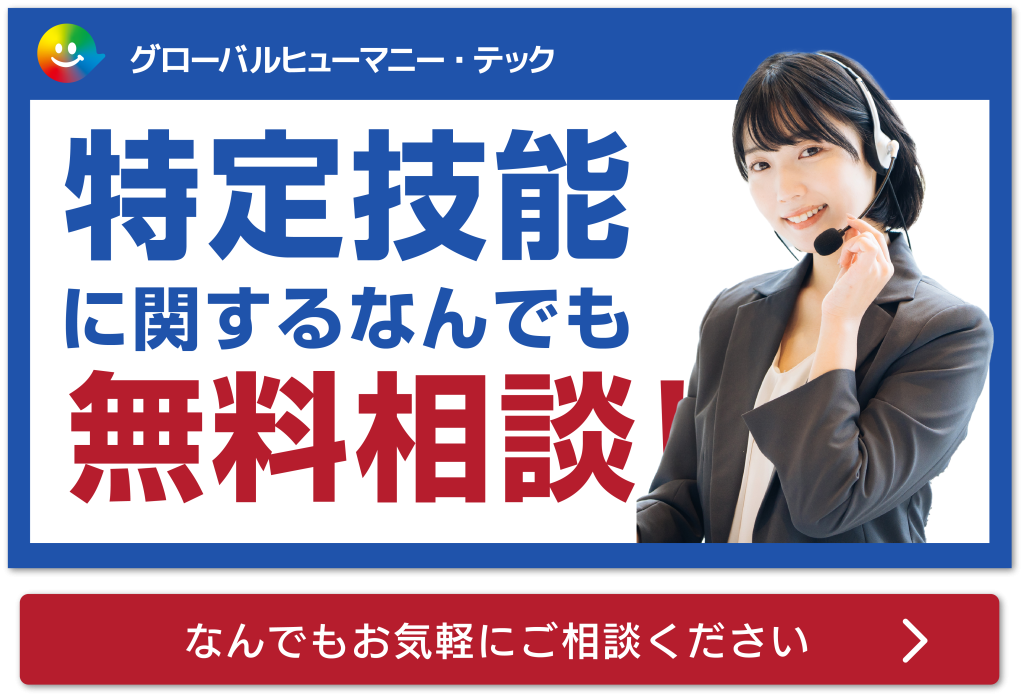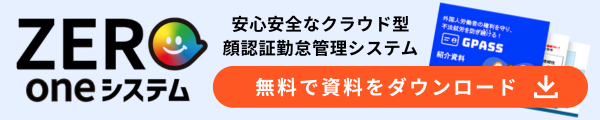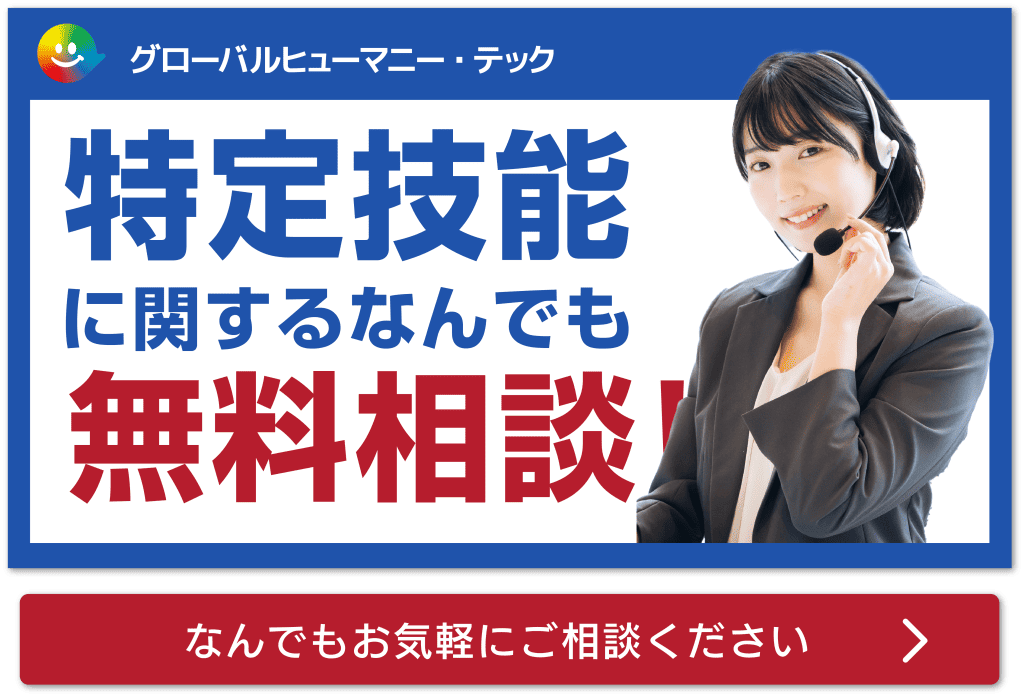外国人労働者の増加に伴い、企業には適切な労務管理が求められています。雇用保険への加入手続きは法令上の義務ですが、在留資格など日本人とは異なる注意点があるため、不安を感じる担当者の方も多いでしょう。
この記事では、外国人労働者の加入条件から、採用・離職時の手続き、法令遵守のために企業が押さえるべき5つの注意点について、網羅的かつわかりやすく解説します。
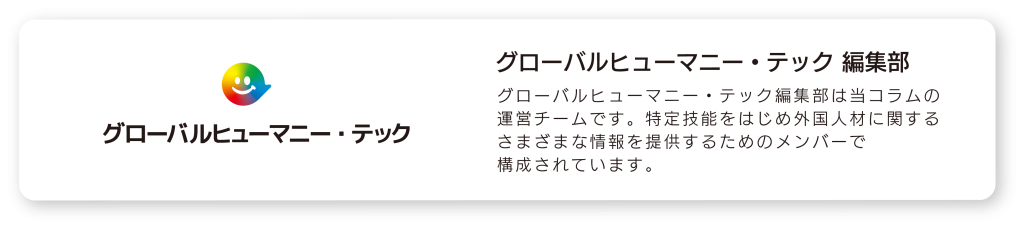
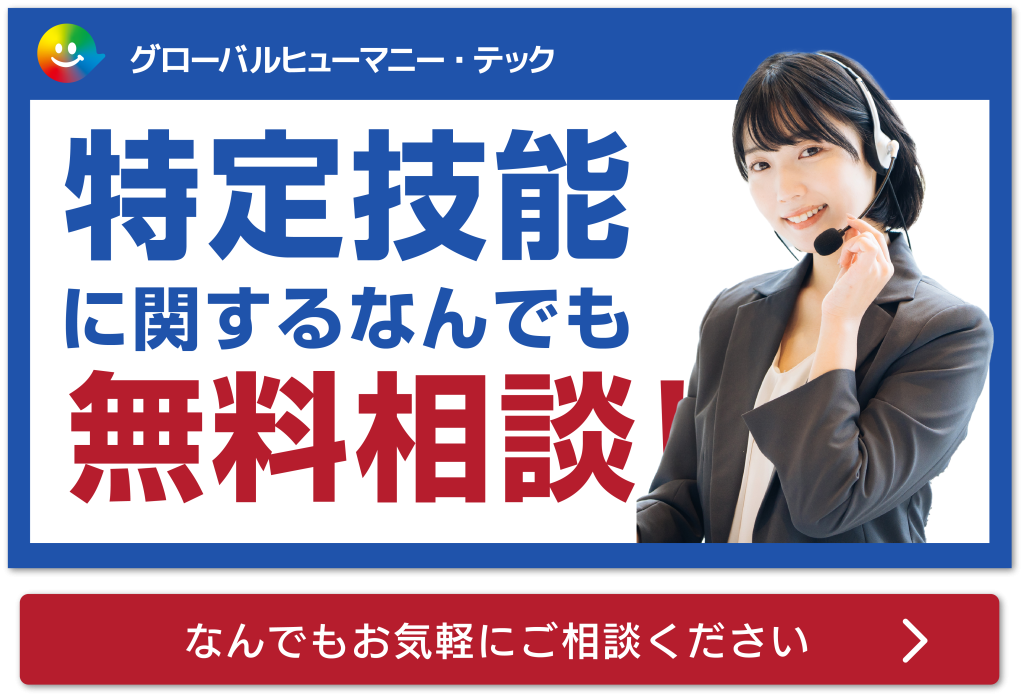
外国人労働者の雇用保険の基本と4つの加入条件
外国人労働者も、日本人労働者と同様に、原則として雇用保険への加入が義務付けられています。雇用保険は、労働者が失業した場合や育児・介護などで休業した場合などに、生活と雇用の安定を図るための給付を行う日本の重要な社会保障制度です。
外国人労働者を雇用保険の被保険者とするための基本的な条件は、以下の4つの要件をすべて満たすことです。これらの条件を満たした場合は、本人の意思に関わらず、企業側が加入手続きを行う義務があります。
1. 週の所定労働時間が20時間以上であること
雇用保険に加入するための最も基本的な条件の一つが、1週間の所定労働時間が20時間以上であることです。この所定労働時間とは、労働契約や就業規則などで定められた契約上の労働時間を指します。
実労働時間が一時的に20時間を超えたとしても、契約上の所定労働時間が20時間未満であれば原則として加入対象外となります。逆に、欠勤や遅刻などがあったとしても、契約上の所定労働時間が20時間以上であれば加入対象です。
2. 31日以上の雇用見込みがあること
雇用契約において、31日以上の雇用見込みがあることも加入の必須条件です。これは、契約書に「契約更新の可能性あり」と記載されている場合や、過去に同様の雇用契約で31日以上雇用された実績がある場合などが該当します。
たとえば、試用期間が30日間であっても、その後の本採用が予定されており、全体で31日以上の雇用が見込まれる場合は加入対象です。逆に、契約更新の定めがなく、31日未満で雇用が終了することが明確な場合は、原則として加入対象外となります。
また、短期のアルバイトやパートの外国人労働者であっても、上記の要件を満たす場合は加入の対象となるため、雇用形態にかかわらず、契約内容に基づいて判断しなければなりません。
3. 在留資格が「外交」「公用」以外であること
外国人労働者のうち、雇用保険の被保険者となる対象者は、日本の国籍を有しない方のうち、在留資格が「外交」または「公用」ではない方です。これらは、日本政府や国際機関等での活動を行うための在留資格であり、その性質上、雇用保険の適用から除外されています。
これらを除く、就労可能な在留資格(例:技術・人文知識・国際業務、特定技能など)を持つ中長期在留者はもちろん、就労が一部認められている留学生や家族滞在の在留資格を持つ方も、上記の労働条件を満たせば加入の対象となります。
なお、特別永住者については、特別の法的地位が与えられているため、外国人雇用状況の届出の対象外となる点も覚えておきましょう。
4. 適用除外の対象者に該当しないこと
上記の条件を満たしていても、雇用保険法によって加入が適用除外とされる特定のケースに該当する場合は被保険者とはなりません。代表的な適用除外者は、昼間部の学校に通う学生や、季節的に一定期間のみ雇用される方などです。
ただし、学生であっても、卒業見込証明書を有し卒業前から同一事業所に勤務し続ける予定の者、休学中の者、夜間学生などは例外的に被保険者となるケースがあります。
また、ワーキングホリデー制度による入国者も、原則として雇用保険の適用は除外されます。適用除外の判断は複雑なケースがあるため、不安な場合はハローワークなどの公的機関に確認しましょう。

外国人労働者の雇用保険における日本人との3つの違い
外国人労働者を雇用保険に加入させる際の手続きや注意点には、日本人労働者と共通する部分が多い一方で、外国人特有の届出事項や在留資格に関する重要な違いが存在します。ここからは、主な違いについてご紹介します。
1. 資格取得届に記載が必要な情報が多い
外国人労働者が雇用保険の被保険者となる場合、企業は雇用保険被保険者資格取得届を管轄のハローワークに提出します。この書類自体は日本人労働者と同じものを使用しますが、外国人労働者の場合は、以下の追加情報を「備考欄」や所定の欄に記載する必要があります。
具体的には、氏名(ローマ字)、国籍・地域、在留資格、在留期間、そして資格外活動許可の有無などです。これらの情報は、在留カードに記載された内容と正確に一致している必要があります。
とくに、在留資格「特定技能」や「特定活動」の場合は、さらに活動分野や類型まで詳細に記載する必要があるため、間違いがないよう注意が必要です。
2. 「外国人雇用状況の届出」が義務付けられている
企業が外国人労働者を採用し、または離職させる際には、その者の氏名や在留資格などについてハローワークへ届け出ることが労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律によって義務付けられています。これが、外国人雇用状況の届出です。
雇用保険に加入する外国人労働者の場合、この外国人雇用状況の届出は、雇用保険の資格取得届や資格喪失届の備考欄に、国籍や在留資格などの必要事項を記載することで、代替して行ったと見なされます。
この代替措置により、企業は二重の手続きを避けられるため、雇用保険の手続きと同時に、必要事項を漏れなく記載することが重要です。届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となる可能性があります。
3. 離職後の失業給付の受給要件に在留資格が関係する点
外国人労働者も、雇用保険の被保険者期間が原則12ヶ月以上などの要件を満たせば、離職時に失業給付(基本手当)を受け取れます。しかし、給付を受けるためには積極的な求職活動を行う必要があり、これが在留資格の維持と密接に関わってきます。
就労系の在留資格(就労ビザ)を持つ外国人は、退職後、3ヶ月以上無職の状態が続いたり、就職活動を行っていないと判断された場合、在留資格が取り消される可能性があります。失業給付の受給期間中であっても、再就職を果たすことが在留資格を維持するための最重要課題となるため、離職者はこの点を理解し、企業側も適切な情報提供を行うのが望ましいです。

企業が雇用保険手続きで遵守すべき5つの注意点
外国人労働者の雇用保険に関する手続きは、日本人労働者と同様の法令に則って行われますが、とくに、在留資格や届出義務に関しては、日本人とは異なる独自の注意点が存在します。企業のコンプライアンスを確保し、労使双方にとって円滑な雇用関係を維持するために、以下の5つの重要事項の遵守が求められます。
1. 雇入れ時の手続き期限を厳守する
企業は、外国人労働者が雇用保険の被保険者となった日(原則として雇入れ日)の属する月の翌月10日までに、管轄のハローワークへ雇用保険被保険者資格取得届を提出する必要があります。
この期限は日本人労働者と同じですが、外国人労働者の場合は、先述の通り国籍や在留資格などの追加情報を漏れなく記載しなければなりません。期限を過ぎてしまうと、遡及して加入手続きを行うことになり、過去の保険料の納付が発生するなど、企業側の事務負担が増大します。
また、法令遵守の観点からも、期限厳守は企業にとって非常に重要です。
2. 在留カードと在留資格を正確に確認する
雇用保険の資格取得届や離職時の資格喪失届には、外国人労働者の在留資格や在留期間などを正確に記載する必要があります。これらの情報は、在留カードに記載されているため、採用時に必ず原本を提示してもらい、その内容を正確に確認することが不法就労の防止にもつながります。
記載内容に誤りがあると、手続きが受理されないだけでなく、外国人雇用状況の届出義務も同時に果たせない可能性があります。人事・労務担当者は、在留カードの有効期限や在留資格の活動制限を常に確認する体制を整えておきましょう。
なお、おすすめの外国人雇用管理システムについては、こちらの記事で詳しくご紹介しています。
関連記事:【2025年最新版】外国人雇用管理システムのおすすめ10選|主な機能や選び方もご紹介!
3. 離職票の発行意思を必ず確認する
外国人労働者が離職する際、企業は管轄のハローワークへ雇用保険被保険者資格喪失届を提出します。この時、労働者が失業給付の受給を希望する場合は、離職票(雇用保険被保険者離職票)の発行が必要となります。
離職票の発行には、離職証明書を資格喪失届と同時に提出しなければならないため、企業は退職者に対し、離職票の発行を希望するかどうかを必ず確認し、希望があった場合は退職日の翌日から10日以内に手続きを完了させる必要があります。
4. 離職時には所属機関の変更届出を促す
外国人労働者が就労系の在留資格を持っており、企業を退職した場合は、退職者本人が地方出入国在留管理官署(入管)に対し、所属機関の変更に関する届出を行う必要があります。これは、法律で定められた本人の義務であり、怠ると在留資格の取り消しにつながる可能性がある重要な手続きです。
企業側の直接的な義務ではありませんが、離職時のサポートとして、この届出の必要性と期限(退職日から14日以内)を本人に伝えることは、適切な雇用管理の一環として非常に重要です。
また、企業側も、雇用保険の資格喪失届の提出によって外国人雇用状況の離職の届出を代替できますが、入管への届出はまた別の手続きであるため、混同しないように注意が必要です。
5. 外国人雇用状況の離職の届出期限を把握する
雇用保険の被保険者であった外国人労働者が離職した場合、企業は雇用保険被保険者資格喪失届を離職日の翌日から10日以内にハローワークへ提出します。この提出の際、資格喪失届の備考欄に国籍・地域、在留資格、在留期間などの情報を正しく記入すれば、外国人雇用状況の離職の届出を代替できます。
しかし、もし外国人労働者が雇用保険の被保険者でなかった場合(例:週の所定労働時間が20時間未満など)、企業は別に外国人雇用状況届出書を作成し、離職日の翌月の末日までにハローワークへ提出しなければなりません。雇用保険の加入有無によって届出方法と期限が異なるため、正確な把握が不可欠です。

外国人採用の相談なら「グローバルヒューマニー・テック」

株式会社グローバルヒューマニー・テックでは、グローバル人材に対する総合的な生活支援を実施しています。豊富な実績による盤石なサポート体制とIT技術をかけ合わせた独自のノウハウで、外国人労働者の支援プラットフォームを充実させています。
外国人材の安心安全な採用支援はもちろん、就業支援や生活支援を通じて人手不足をグローバルソリューションで解決するのが私たちの使命です。⇒株式会社グローバルヒューマニー・テックに相談する

外国人の雇用保険でよくある3つの質問
外国人の雇用保険でよくある質問を3つご紹介します。それぞれの内容について詳しくみていきましょう。
質問1. 留学生のアルバイトも雇用保険に加入する必要がありますか?
原則として、昼間部の学校に通う留学生は、学業が本分であると見なされ、雇用保険の適用除外となります。そのため、アルバイトであっても基本的には加入の義務はありません。ただし、例外的なケースとして、以下のいずれかに該当する場合は、雇用保険の被保険者となるケースがあります。
たとえば、休学中である場合や、夜間学生である場合、または卒業見込証明書を有し、卒業後も引き続き同一の事業所で働くことが内定している場合などです。企業側は、留学生を雇用する際に在学証明書などを確認し、適用除外となる学生に該当するかどうかを正確に判断する必要があります。
質問2. 外国人が退職した際、会社が行う雇用保険の手続きは日本人と何が違いますか?
外国人労働者が退職した際、企業が行う雇用保険の手続き(資格喪失届の提出、離職票の交付など)は、基本的に日本人労働者の場合と同様です。しかし、外国人特有の手続きとして、外国人雇用状況の離職の届出が義務付けられています。
この届出は、雇用保険の被保険者であった外国人の場合は、雇用保険被保険者資格喪失届の備考欄に、国籍・地域、在留資格などの必要事項を記載することで代替できます。この代替措置により、ハローワークへの届出は一本化されますが、備考欄の記載漏れは法令違反となり得るため、日本人従業員以上に正確な情報の記載が必要です。
質問3. 雇用保険に加入していない外国人が離職した場合、企業は何を届け出る必要がありますか?
雇用保険に加入していない外国人労働者が離職した場合でも、企業には外国人雇用状況の離職の届出の義務があります。この場合、雇用保険の資格喪失届で代替することはできないため、企業は外国人雇用状況届出書を作成し、管轄のハローワークへ提出しなければなりません。
届出期限は、離職日の翌月の末日までです。この届出は、雇用対策法に基づく企業の責務であり、適切な雇用管理を行う上で不可欠な手続きとなります。雇用保険の加入の有無にかかわらず、外国人労働者の雇入れと離職の際には届出義務が発生する旨を覚えておきましょう。

まとめ
外国人労働者の雇用保険への加入は、国籍を問わず、所定の要件を満たす全ての人に義務付けられている企業の重要な責務です。週の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みがある場合は、原則として雇用保険の被保険者となります。
日本人と異なる点として、資格取得届や資格喪失届に国籍・在留資格などの追加情報を正確に記載する必要があること、そして外国人雇用状況の届出義務が発生することが挙げられます。
とくに、離職時の手続きにおいては、雇用保険の加入有無によって提出すべき書類や期限が異なるため、人事・労務担当者は、在留カードの情報に基づき、法令遵守を徹底した正確な手続きが求められます。
なお、株式会社グローバルヒューマニー・テックでは、グローバル人材に対する総合的な生活支援を実施しており、外国人の受け入れにおける豊富な経験と知識を有しています。ご相談・お見積りはもちろん無料です。まずはお気軽にお問合せください。⇒株式会社グローバルヒューマニー・テックに相談する