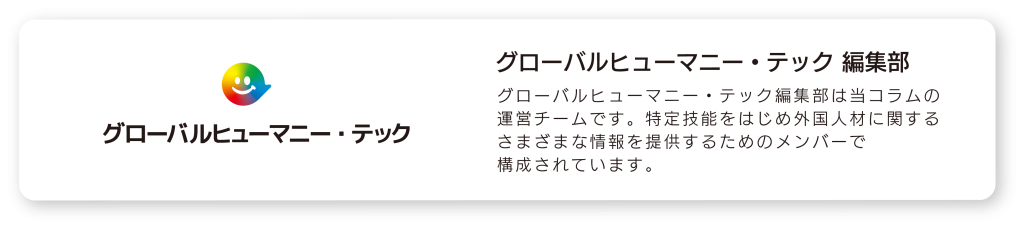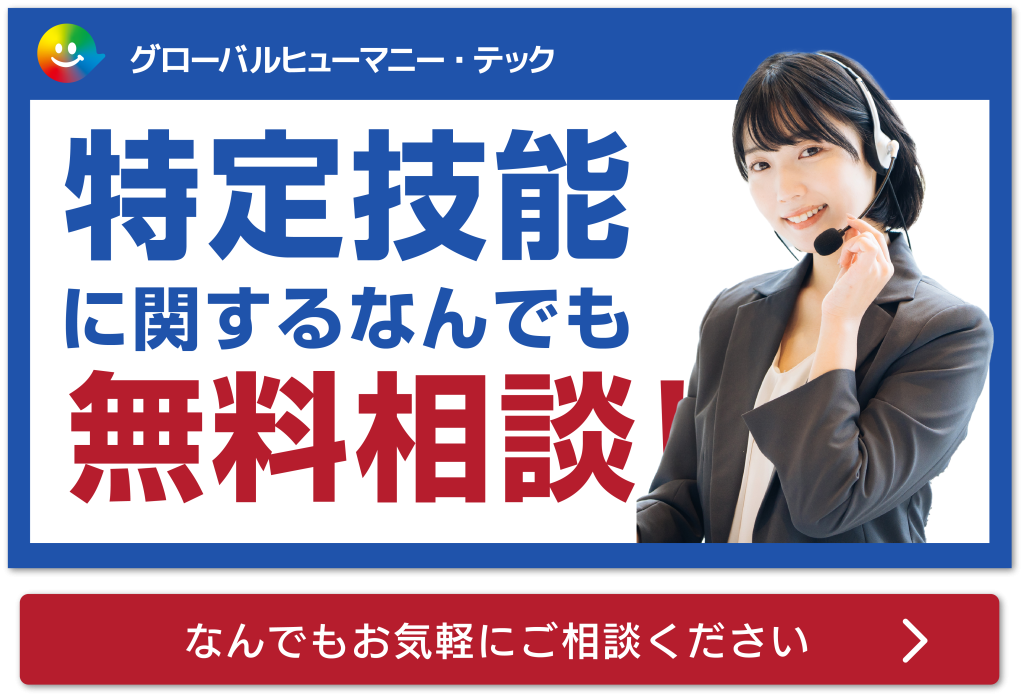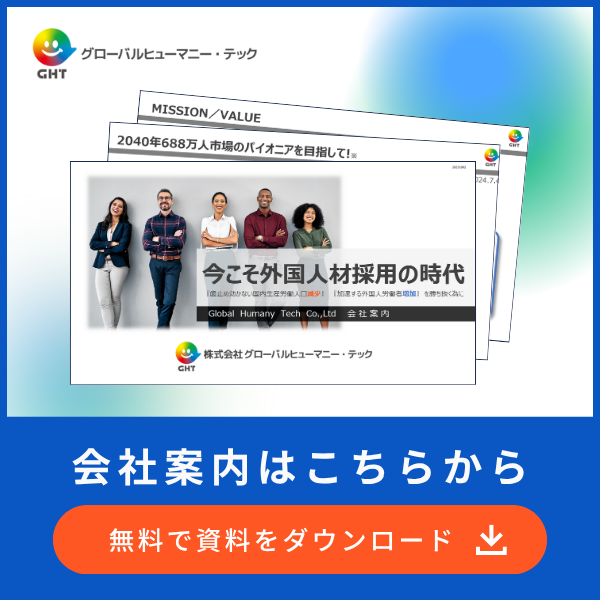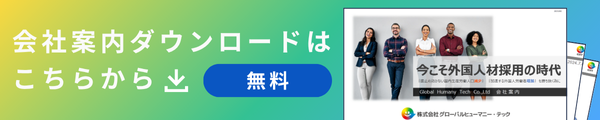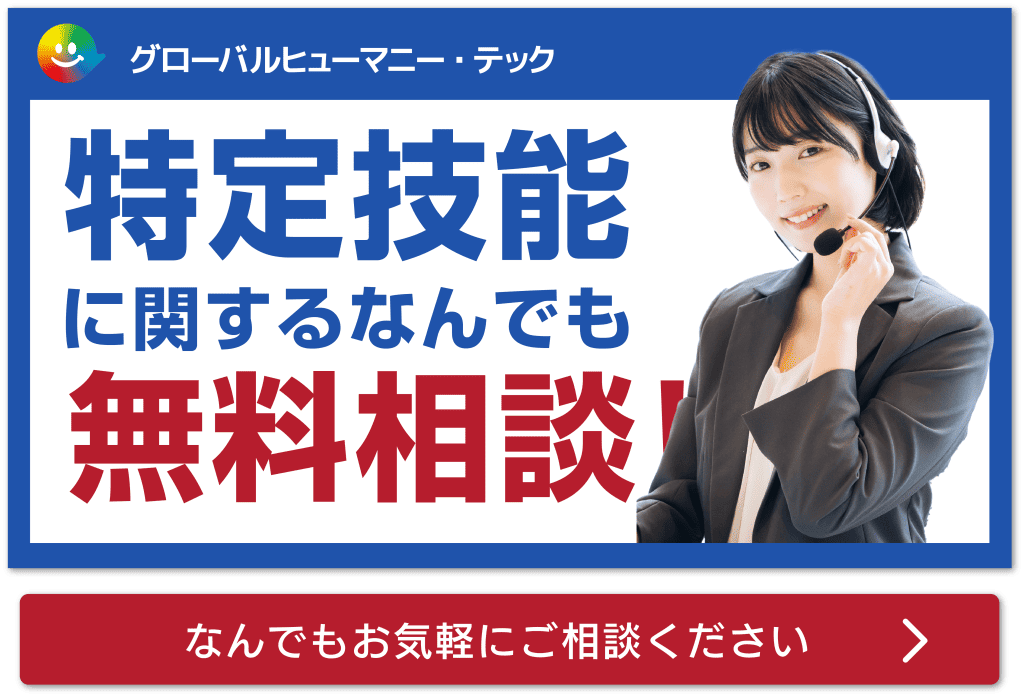外国人を雇用する企業にとって、「不法就労助長罪」は、企業活動の継続に深刻な影響を及ぼす重大なリスクです。この罪は、故意だけでなく、外国人の在留資格の確認を怠った「過失」によっても成立する可能性があるため、決して他人事ではありません。
本記事では、不法就労助長罪の構成要件から、初犯で問われる刑罰の相場、そして企業の信用と事業の継続を守るために不可欠なコンプライアンス体制の強化策まで、網羅的に解説します。この記事を読めば、適切な外国人雇用に向けた具体的な一歩を踏み出せます。
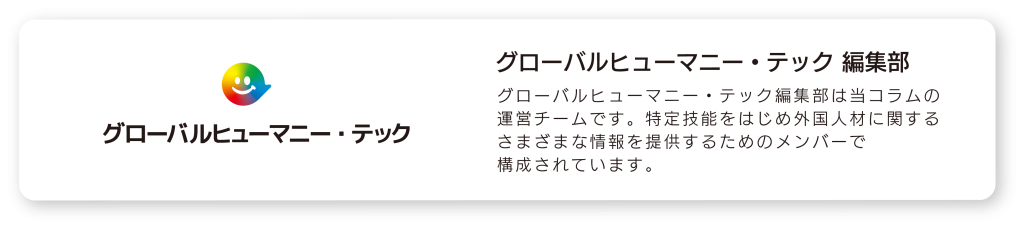
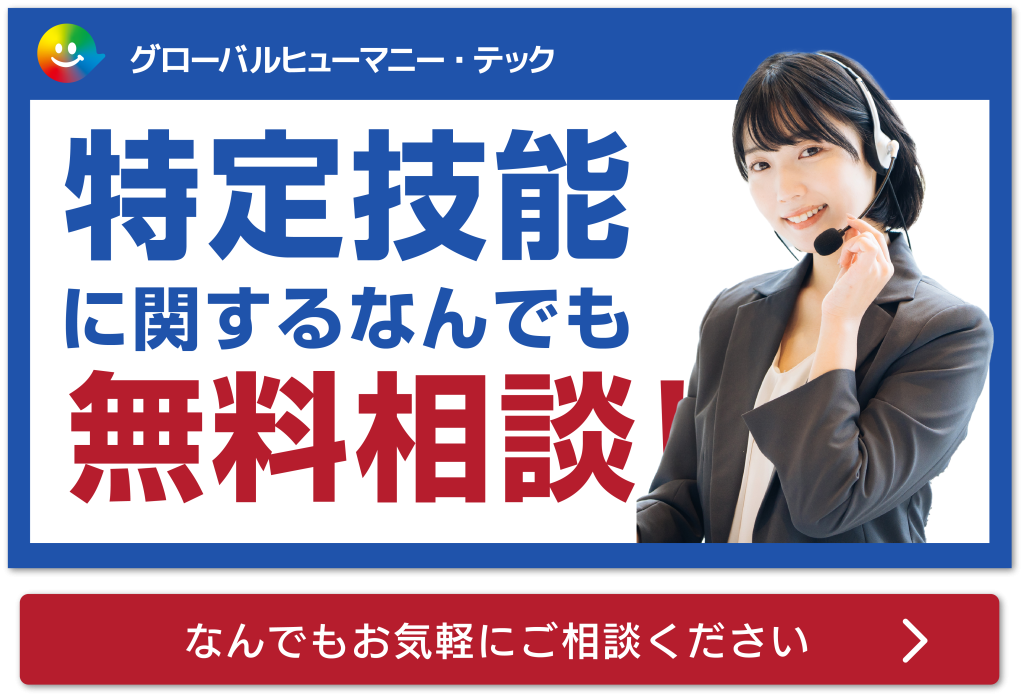
不法就労助長罪の構成要件と罰則の内容
まずは、不法就労助長罪がどのような行為に対して成立するのかという構成要件と、違反した場合に科される罰則の基本について、3つの観点から解説します。
1. 不法就労助長罪の定義と3つの類型
不法就労助長罪とは、事業活動に関連して、不法就労活動を行う外国人を雇用したり、斡旋したりする行為を取り締まるための罪です。出入国管理及び難民認定法(入管法)第73条の2第1項に規定されており、外国人の不法就労を防止し、日本の労働市場の適正な維持を図ることを目的としています。
この罪は、以下の3つの類型に該当する行為が処罰の対象となります。
- 自らの事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせること
- 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと
- 業として、上記2つの行為をあっせんすること
とくに、在留資格を持たない外国人を雇う行為や、与えられた在留資格の範囲を超えた活動をさせる行為は、この罪に該当する代表的なケースであり、企業側には、外国人を雇用する際に、単に在留カードの有無だけでなく、在留資格の種類、在留期間、そして資格外活動許可の有無と範囲を厳格に確認する注意義務があります。
2. 「不法就労活動」の定義
不法就労助長罪の前提となる「不法就労活動」には、正規の在留資格を持たない外国人の収入を伴う活動と、正規の在留資格を持つ外国人でも許可なく行う活動の2つのパターンが含まれます。
前者には、密入国者やオーバーステイ(不法残留)の外国人が働くケースなどが該当します。後者には、就労が認められていない在留資格(例:留学、家族滞在など)を持つ外国人が、資格外活動の許可を受けずに働くケースや、認められた活動範囲を超えて働くケースが該当します。
この確認を怠った場合、故意でなくとも過失として処罰の対象となり得るため、企業側の厳格なコンプライアンスの体制が不可欠です。
なお、オーバーステイの罰則については、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事:オーバーステイの罰則とは?オーバーステイの外国人雇用を防ぐためのポイントもご紹介!
3. 不法就労助長罪の法定刑と法人に対する罰則
不法就労助長罪の法定刑は、現状では「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定められています。
また、この罪には両罰規定が適用されるため、行為者である個人(社長や担当者など)が処罰されるだけでなく、その法人(会社)に対しても罰金刑が科される可能性があります。

不法就労助長罪の初犯で問われる3つの刑罰の相場
不法就労助長罪は、初犯であってもその事案の悪質性によっては重く処罰される可能性があります。ここでは、初犯で直面する可能性のある3つの主要な刑罰とその相場について解説します。
1. 罰金刑の相場と実務上の考慮事項
初犯で、かつ不法就労させた外国人の人数が少ない場合など、事案の悪質性が低いと判断されるケースでは、罰金刑が科されるのが一般的です。罰金刑は、懲役刑や拘禁刑のような身体拘束を伴う刑罰ではないものの、前科として記録されます。
法定刑の上限は500万円ですが、初犯であれば数十万円から数百万円の範囲で罰金が命じられるのが相場です。しかし、法人と個人に併科された場合、罰金の総額はさらに大きくなります。
量刑の際には、雇い入れた外国人の人数、不法就労の期間、企業側の認識(故意か過失か)、そして摘発後の改善措置の有無が、罰金額に影響を与える重要な考慮事項です。
2. 執行猶予付き判決となるための重要要素
初犯の場合、懲役刑が避けられない事案であっても、すぐに刑務所に収容される実刑ではなく、「執行猶予付き判決」となる可能性が高いです。執行猶予とは、懲役刑の判決を下しながら、一定期間(通常3〜5年)その刑の執行を猶予する制度であり、この期間中に再び罪を犯さなければ、刑の言い渡し自体が効力を失います。
執行猶予を得るために最も重要なのは、反省の態度を示し、不法就労の経緯を正直に説明し、再発防止のための具体的なコンプライアンス体制の構築など、情状を有利にする活動を行うことです。
3. 初犯でも実刑判決を受ける可能性と事案の特徴
不法就労助長罪は、初犯であっても実刑判決(懲役刑や拘禁刑)を受ける可能性が十分にあります。とくに、多数の不法就労者を組織的かつ継続的に雇用していた場合、不法就労によって得た利益が非常に大きい場合、あるいは不法就労者のパスポートを取り上げて支配下に置くなど、人権侵害を伴う悪質な手口があった場合などは、悪質性が高いと判断され、厳しく処罰される傾向があります。
初犯であることが有利な事情として考慮される場合もありますが、上記のような悪質な事情が伴うと、その有利な事情も打ち消されてしまうため、過去には「懲役1年10か月」の判決が下されたケースも報告されており、決して油断はできません。

不法就労助長罪をめぐる企業がとるべき3つの対策
不法就労助長罪で摘発されないためには、企業として外国人雇用に関するリスク管理を徹底しなければなりません。ここでは、そのために必要な3つの具体的な対策を解説します。
1. 雇用前の在留資格の厳格な確認手順
不法就労助長罪が過失でも成立し得ることを踏まえ、外国人を雇用する際には、在留資格の確認を厳格に行う必要があります。具体的には、必ず在留カードの原本を提示させ、カードの偽造がないか、記載されている在留期間が有効であるかを確認します。
さらに、カードに記載された在留資格が、採用しようとしている業務内容と合致しているかを確認し、留学生など就労に制限がある場合は、「資格外活動許可」を受けているか、またその活動範囲(例:週28時間以内)を超えていないかを厳しく確認しなければなりません。
確認した在留カードの両面のコピーをとり、確認日と確認者の氏名を記載して、雇用契約書などと共に保管することが、注意義務を果たした証拠として推奨されます。
なお、不法滞在者の特徴と見分け方については、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事:不法滞在者の特徴と見分け方とは?外国人を雇用する際に注意すべきポイントを徹底解説!
2. 雇用後の定期的な在留状況の管理と届出
在留資格は更新や変更が行われるため、雇用後も定期的な管理が必要です。雇用している外国人の在留期間を台帳などで管理し、期限が切れる前に更新手続きを促すなど、オーバーステイ(不法残留)とならないよう、企業側が積極的にサポートし、管理しなければなりません。
また、労働施策総合推進法に基づき、外国人(特別永住者、在留資格が「外交」「公用」の者を除く)の雇用開始時および離職時に、氏名、在留資格などをハローワークに届け出る義務があります。
この届出を怠ったり、虚偽の届け出をしたりした場合も、30万円以下の罰金に処される可能性があるため、適切な管理が不可欠です。
3. 法令違反が判明した場合の初期対応と弁護士への相談
万が一、不法就労の疑いが生じた場合、迅速かつ適切な初期対応が、その後の刑事処分に大きな影響を与えます。判明した時点で直ちに当該外国人の就労を停止させ、入管当局への報告を含めた是正措置を講じる必要があります。
また、警察や入管の捜査に備え、関連する雇用契約書、在留カードのコピー、給与台帳などの証拠を保全することが重要です。捜査が開始された場合、初犯であっても逮捕や書類送検の可能性を伴うため、企業側は、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談することが極めて重要です。
弁護士は、捜査への対応、不起訴処分や執行猶予付き判決獲得に向けた情状証拠の収集、再発防止策の策定などをサポートし、企業と経営者を守るための活動を行います。

外国人採用の相談なら「グローバルヒューマニー・テック」

「株式会社グローバルヒューマニー・テック」は、グローバル人材に対する総合的な生活支援を実施しています。外国人材の安心安全な採用支援、就業支援や生活支援を通じて、企業の人手不足をグローバルソリューションで解決することをミッションとしています。
豊富な実績による盤石なサポート体制とIT技術をかけ合わせた独自のノウハウで、外国人労働者の支援プラットフォームを充実させている点が強みです。これにより、単なる人材紹介にとどまらず、外国人材が日本で安心して生活・就労できる環境を総合的にサポートしています。⇒株式会社グローバルヒューマニー・テックに相談する

不法就労助長罪の初犯でよくある3つの質問
不法就労助長罪の初犯でよくある質問を3つご紹介します。それぞれの内容について詳しくみていきましょう。
質問1. 不法就労助長罪は「知らなかった」場合でも成立しますか?
不法就労助長罪は、原則として故意犯ですが、外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、企業側に過失があった場合は処罰の対象となり得ます。
たとえば、在留カードの有効期限や、就労可能な在留資格であるかを確認する注意義務を怠った場合、その過失によって不法就労を助長したと判断される可能性があります。企業は、在留カードの原本確認とそのコピーの保管を徹底するなど、外国人雇用の適正化に向けた管理体制を構築しなければなりません。
質問2. 不法就労助長罪で逮捕された場合、会社名や氏名は公表されますか?
不法就労助長罪で逮捕された場合や書類送検された場合、その事案が社会的に注目されるものであれば、警察や報道機関によって会社名や氏名が公表されるリスクがあります。公表されることで、企業の信用が大きく損なわれ、取引先からの契約解除や、採用活動への悪影響など、事業継続に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
初犯であっても、事案の悪質性や社会的な影響の大きさによっては公表の対象となるため、初期対応から弁護士に相談し、可能な限り不起訴処分を目指すなど、公表のリスクを最小限に抑える活動が重要となります。
なお、不法就労助長罪の事例については、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事:【2025年最新】不法就労助長罪の事例3選|外国人を雇用する際に知っておきたいポイントもご紹介!
質問3. 不法就労助長罪と外国人雇用状況の届出義務違反は違いますか?
不法就労助長罪と外国人雇用状況の届出義務違反は、どちらも外国人雇用に関する法令違反ですが、根拠法と罰則が異なります。不法就労助長罪は入管法に基づく罪で、懲役または罰金という重い刑事罰が科されます。
一方、外国人雇用状況の届出義務違反は労働施策総合推進法に基づくものであり、届出を怠ったり虚偽の届出をしたりした場合に、30万円以下の罰金が科せられる行政罰です。届出義務違反は不法就労助長罪ほど重い罪ではありませんが、企業としてコンプライアンスを徹底し、適正な雇用管理を行うためには、両方の法令を遵守する必要があります。

まとめ
不法就労助長罪の法定刑は「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はその併科」という極めて重いものであり、初犯であっても実刑判決や罰金刑が科されるリスクが十分にあります。
とくに、企業だけでなく個人にも両罰規定が適用される点、そして故意でなくても在留資格の確認を怠った「過失」によって成立し得る点は、経営者や担当者として最も注意すべきポイントです。
企業の信用を守り、事業の継続性を確保するためには、外国人雇用の全段階における在留カードの厳格な確認と、在留状況の管理の徹底、法令遵守(コンプライアンス)の体制強化が欠かせません。不法就労助長罪は、企業の存続に関わる問題であると認識し、適切なリスク管理を行ってください。
株式会社グローバルヒューマニー・テックは、外国人の受け入れにおける豊富な経験とノウハウを持ち、企業が抱える課題を解決に導きます。グローバル人材に対する総合的な生活支援も実施しているため、外国人が安心して日本で働けるよう、多角的にサポートします。⇒株式会社グローバルヒューマニー・テックに相談する