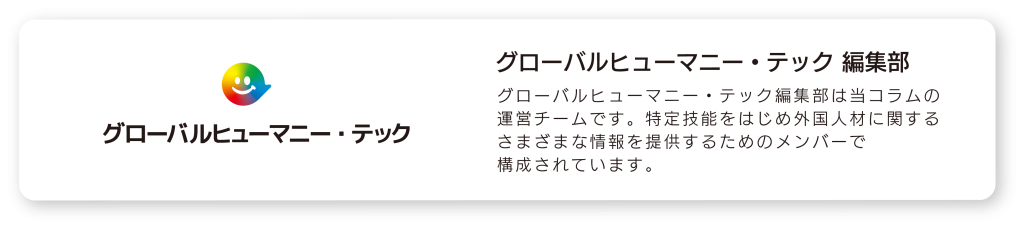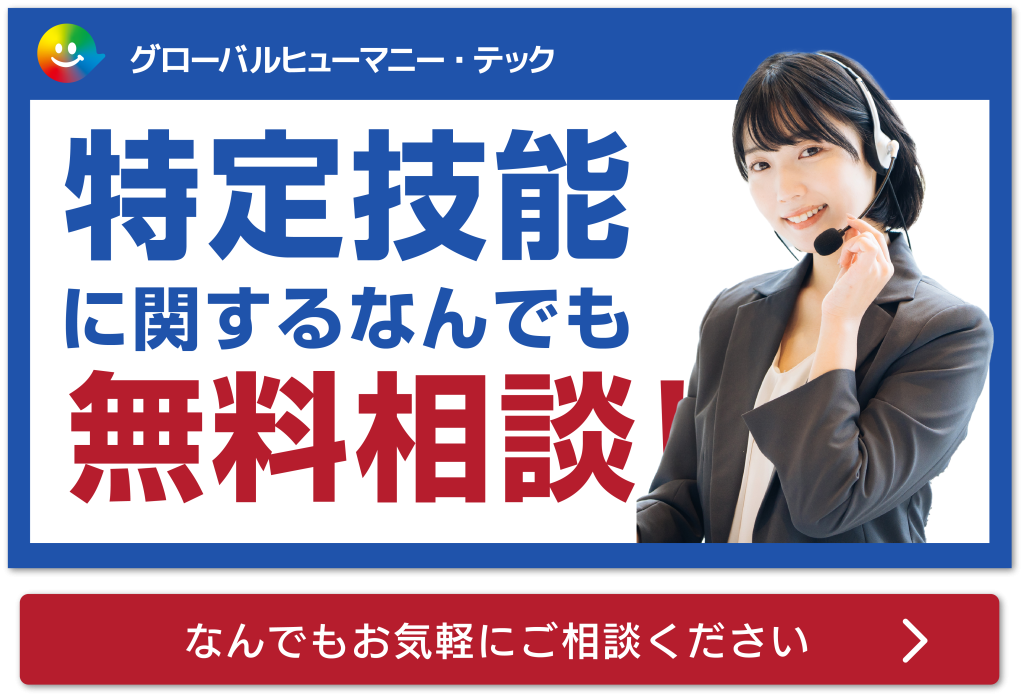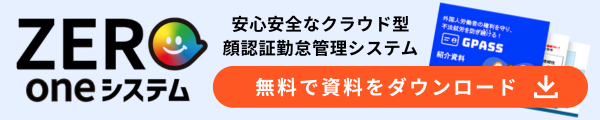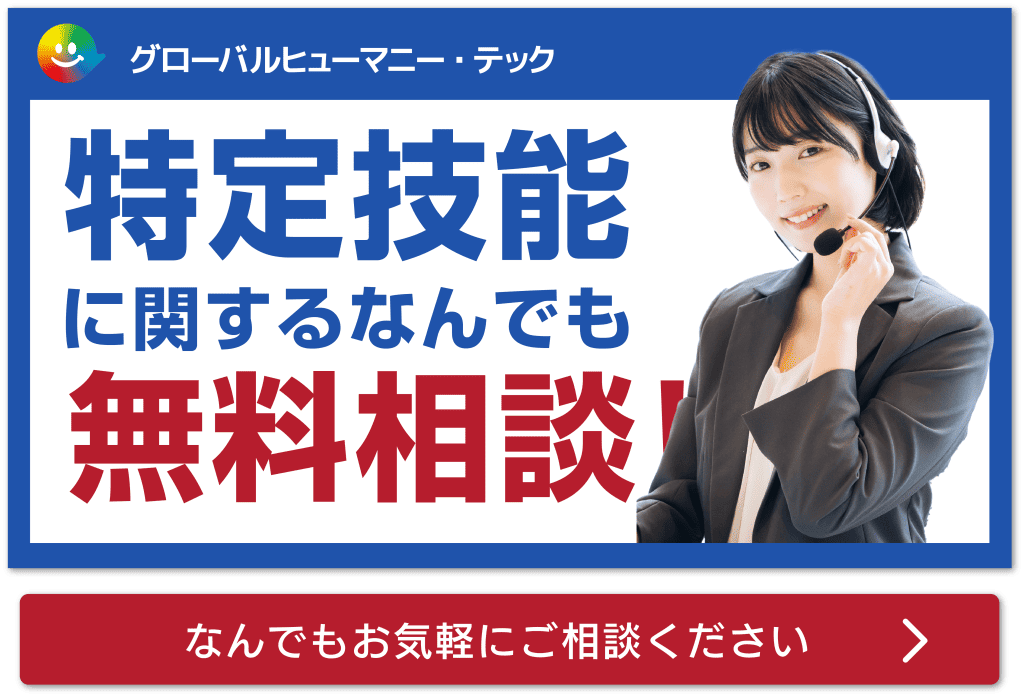日本の高齢化が進むなか、介護業界は社会全体で考えるべき課題に直面しています。人手不足や利用者の増加、介護職員の負担といった現場の問題に加え、制度や地域格差など、さまざまな社会の課題があり、解決策が急務となっている状況です。
本記事では、介護業界の課題や介護における社会問題、課題解決に向けた取り組みをご紹介します。また、よくある質問も解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
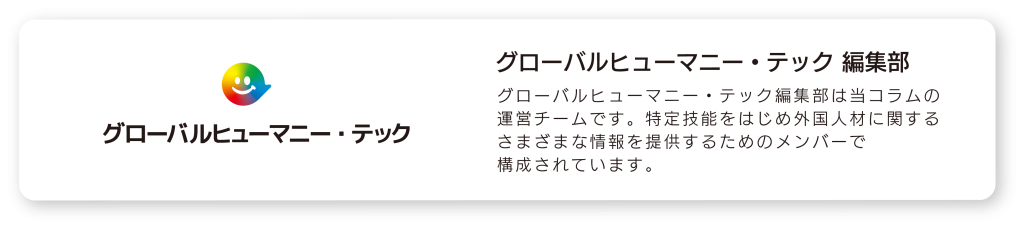
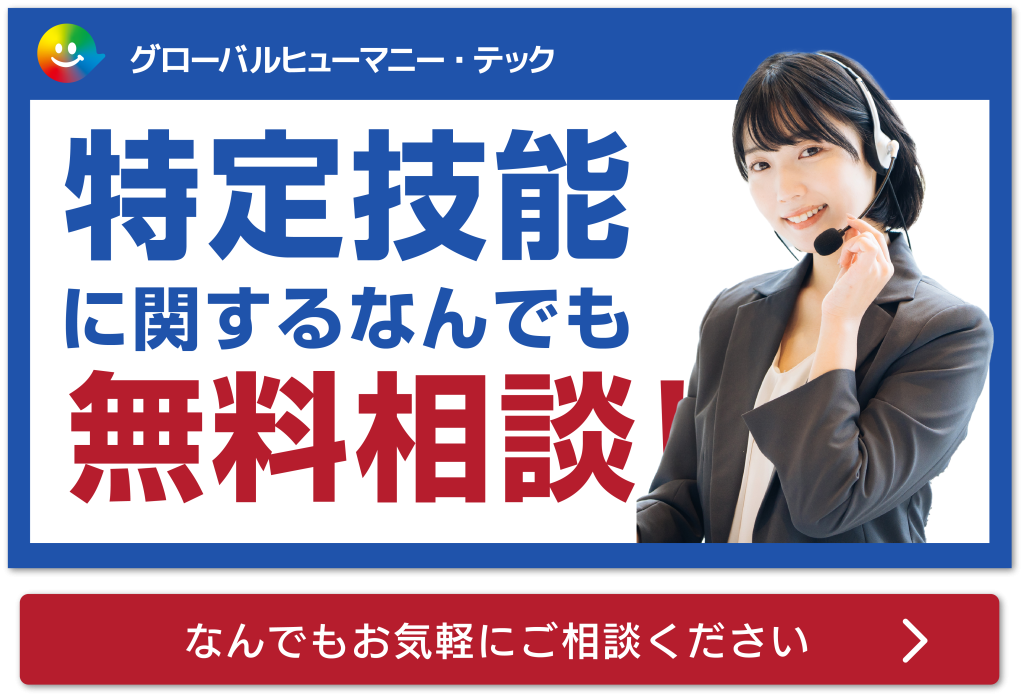
介護業界の課題とは?
2025年問題とは、日本社会における重要な課題であり、高齢者人口の増加とそれに伴う影響について多方面で議論されています。1947年から1949年に生まれた団塊世代が75歳以上の後期高齢者に到達することで、社会全体の高齢化が加速する状況が指摘されています。
内閣府のデータによると、高齢者人口は増加を続け、2025年には総人口の約30%を占める見込みです。さらに、高齢化率はその後も上昇し、2065年には約38%に達すると予測されています。
また、認知症高齢者の増加や、独居高齢者の問題が深刻化しており、介護や医療の需要が急増して、現役世代への負担が大きくなる点が懸念されています。これらの状況下では、持続可能な社会の実現に向けた新たな政策や対策が必要です。

介護における5つの社会問題
次は、介護における5つの社会問題について解説します。
- 高齢者の一人暮らし
- 介護人材の不足
- 老老介護・認認介護
- 社会保障の財源不足
- ヤングケアラー問題
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
1.高齢者の一人暮らし
高齢者が一人で生活する背景として、配偶者の死別や離婚、長年独身で過ごしてきたなど、個々の事情によるものがあります。一人暮らしは自由ですが、加齢とともに日常生活の維持が難しくなるリスクを伴います。
はじめは自立していても、体力の低下により掃除や洗濯といった家事が困難になり、さらには認知症の進行や健康上の問題が生じかねません。このような状況に備えるため、介護サービスや自治体の支援の積極的な活用が求められます。
また、住環境の見直しも大切で、バリアフリー化や生活動線の改善により、安全で快適な暮らしを保つ工夫が必要です。高齢者が安心して生活するためには、支援体制の整備と個人の備えが欠かせません。
2.介護人材の不足
介護業界では、慢性的な人手不足が深刻な課題となっています。とくに都市部では高齢者人口の増加に伴い、介護職員の需要が急激に高まっています。
厚生労働省の統計によると、介護職の有効求人倍率は全職種平均を大幅に上回る水準で推移しており、東京都ではその倍率が全国で一番高い状態です。一方、地方では高齢化の進行が比較的緩やかな地域もあり、地域ごとに対策の優先度が異なるのが現状です。
2040年には全国で約280万人の介護職員が必要と試算されていますが、このままでは約69万人が不足する可能性が指摘されています。職員の年齢層も多様化しており、高齢の介護職員が増えるなかで、業務負担のさらなる増加が懸念されています。このため、人材確保と労働環境の改善が急務です。
参考:第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について|厚生労働省
3.老老介護・認認介護
高齢化が進むなかで、家族間の介護の在り方にも大きな課題が生じています。「老老介護」は、65歳以上の高齢者同士で介護を行う状況を指し、身体的・精神的な負担が大きい点が問題視されています。
また、認知症を抱える高齢者同士が介護を行う「認認介護」も増加傾向にあり、これらの状況は介護体制の見直しが急務です。2012年には「認知症施策推進総合戦略(オレンジプラン)」が策定され、地域での支援体制の強化が進められています。
この計画では、認知症ケアパスの普及や早期診断の推進、地域医療や介護サービスの構築、人材育成などが重視されており、住み慣れた地域での生活を支えることが目標とされています。地域全体の協力が、今後の介護の質向上に不可欠です。
参考:「認知症施策の現状について」|厚生労働省公式HP社保審一介護給付費分科会(第115回H26.11.19)
4.社会保障の財源不足
日本の社会保障制度は、高齢化の進展によって深刻な財源不足の課題に直面しています。介護や医療分野における支出は年々増加しており、少子化により納税者数が減少するなか、持続可能な財源の確保が困難な状況です。
2024年度には社会保障給付費がGDPの約22.4%を占める規模となり、国の財政を圧迫しています。75歳以上の高齢者の増加に伴い、医療や介護にかかる費用は急増し、1人当たりの国庫負担額が大幅に上昇しています。
この現状を受け、国は制度改革を進めていますが、適切な解決策は見つかっていません。応益負担への移行も議論されていますが、サービスの質や公平性に影響を与える可能性が懸念されています。財源確保と負担のバランスが今後の大切な課題となります。
5.ヤングケアラー問題
ヤングケアラーとは、18歳未満の子どもが日常的に家族の世話や介護を担う状況を指しており、近年深刻な社会問題として注目されています。核家族化や共働き家庭の増加などの背景が影響しており、家族のサポートが不足するなかで、子どもが大人の役割を背負わざるを得ないケースが増えています。
このような負担は、子どもの成長や教育の機会を奪い、将来の進路や生活に長期的な影響をおよぼしかねません。厚生労働省の調査でも、多くの自治体でヤングケアラーが確認されており、把握しきれていないケースも存在する可能性が高いです。
子どもたちが安心して学び、成長できる環境を整備するためには、福祉や教育現場での早期介入や、支援の枠組みの強化が急務となります。
参考:令和2年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「ヤングケアラーの実態に関する調査研究報告書」|厚生労働省

介護業界の課題解決に向けた重要な取り組みは5つ
次は、介護業界の課題解決に向けた重要な取り組みについて解説します。
- 介護職員の業務負担の軽減
- 介護士のメンタルケア
- 長時間労働の解消
- IT導入による業務効率化
- 外国人の雇用
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
1.介護職員の業務負担の軽減
介護現場での業務負担を軽減するためには、テクノロジーの活用が重要な役割を果たしています。たとえば、介護ロボットや見守りセンサーは、利用者の安全を確保しながら、職員の身体的・精神的負担を軽減する画期的なツールです。
また、業務の電子化や音声入力技術の導入によって、事務作業の効率が大幅に向上した事例もあります。記録業務をデジタル化すれば、紙媒体の保存が不要となり、インカムを利用した音声入力では記録時間が週に数時間単位で短縮されています。
このような取り組みは、介護職員の労働環境の改善に加え、人材不足の解消にも寄与する可能性が高いです。先進技術の導入が、より効率的で負担の少ない介護現場を実現するポイントになります。
2.介護士のメンタルケア
介護現場で働く職員のメンタルケアは、業務の効率化と職場環境の改善において不可欠な要素です。介護職員は、利用者やその家族との関係、職場内での人間関係、過酷な労働環境から多くのストレスを抱える場合が少なくありません。
このような状況で、感情を抑えながら働く「感情労働」の負担は非常に大きく、バーンアウトや精神的な不調を引き起こす要因となります。職員の心身の健康を守るためには、定期的な個別面談を通じて悩みやストレスの源を把握して、適切なサポートを提供する仕組みが不可欠です。
また、上司や同僚とのコミュニケーションの場を設ければ、心理的安全性を高め、働きやすい環境を整えられます。さらに、パワハラやセクハラへの迅速な対応も欠かせません。
3.長時間労働の解消
介護業界において、長時間労働は依然として大きな課題です。夜勤はその典型であり、16時間勤務が一般的で、実際の労働時間は17~18時間にもおよぶケースがあります。最低限の人員で夜勤を回している状況では、十分な休憩や仮眠が取れず、職員の疲労が蓄積しやすくなります。
このような状況を改善するため、勤務体制の見直しが必要です。たとえば、夜勤勤務者が一目で分かるような識別アイテムを導入すれば、適切な業務管理を実現して、定時での交代を徹底する取り組みが挙げられます。
また、仮眠スペースの整備やシフト管理の効率化により、職員が安心して働ける環境の構築が大切です。このような施策により、長時間労働の解消と職場の持続可能性を高められます。
4.IT導入による業務効率化
介護記録ソフトを活用したペーパーレス化や、パワーアシストスーツの導入により職員の身体的負担が軽減されるなど、IT導入のメリットは多岐にわたります。また、見守りシステムはセンサーやカメラ技術を活用して、利用者の状況を遠隔でモニタリングできる仕組みです。
このため、職員の訪室回数を減らし、休憩時間や記録作成の時間を確保する助けとなっています。一方で、介護現場におけるIT化の進展は十分ではなく、多くの施設がその導入に踏み切れていないのが現状です。
また、政府が提供するICT補助金やIT導入補助金を活用すれば、初期費用を抑えながらデジタル化を進められます。これにより、利用者と職員双方にとって快適な環境の整備が期待できます。
5.外国人の雇用
日本では生産年齢人口の減少に伴い、介護分野における外国人労働者の受け入れが進められています。EPA(経済連携協定)や技能実習、特定技能1号といった複数の受け入れルートが存在します。
EPAでは、主にインドネシアやフィリピン、ベトナムなどから来日した人材が、介護福祉士の資格取得を目指して働きながら学ぶ仕組みです。一方、技能実習制度や特定技能1号は、本国への技術移転や一時的な人材確保を目的としており、就労期間が限られる場合があります。
これらの制度は日本の介護現場を支えていますが、外国人職員の定着や支援体制の充実が今後の課題となっています。
なお、外国人労働者を雇うための5つのステップについては、こちらの記事で解説しています。
関連記事:外国人労働者を雇うための5つのステップ|メリット・デメリットや雇用できる条件をご紹介!

介護業界 課題でよくある3つの質問
最後に、介護業界 課題でよくある3つの質問について紹介します。
- 質問1.介護業界に多い離職理由は?
- 質問2.介護業界で外国人を雇用するメリットは?
- 質問3.在留資格「介護」とは?
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
質問1.介護業界に多い離職理由は?
介護業界では、職場の人間関係が離職理由のなかで大きな割合を占めています。「令和3年度 介護労働実態調査」によると、18.8%の職員が人間関係の悪化を理由に退職しています。業務はチームで行う場合が多いため、人間関係が悪化すると仕事の進行が滞り、ストレスが蓄積しかねません。
この課題に対処するためには、施設が定期的なヒアリングを実施して、職員の悩みや意見を把握しなければなりません。また、結婚や出産といったライフイベントも退職理由のひとつで、柔軟な勤務体制や休暇制度の整備が求められます。
さらに、収入面の不満も14.9%の職員が離職理由として挙げており、給与や福利厚生の見直しが必要です。このように、職場環境の改善と職員のキャリアアップ支援が、離職率の低下につながります。
参考:令和3年度 介護労働実態調査結果について|公益財団法人 介護労働安定センター
質問2.介護業界で外国人を雇用するメリットは?
日本の介護業界では、人手不足解消のために外国人労働者の採用が進んでいます。地方の施設では、応募者が少ない現状を補う手段として注目されています。
厚生労働省のデータによると、2022年〜2023年にかけて4万人以上の外国人が介護分野で活躍しており、若い労働力の確保が可能です。さらに、特定の在留資格を持つ労働者は長期間の就労ができ、継続的なケアを提供できる点が魅力です。
また、在留資格「介護」を持つ外国人は、更新制限がなく、介護福祉士の資格取得により定年までの就労が期待できます。長期的な雇用は、介護の質向上や施設の安定運営に寄与し、職場全体の成長を後押しします。
質問3.在留資格「介護」とは?
2017年9月に新設された在留資格「介護」は、日本の介護業界における外国人雇用の新たな選択肢として注目されています。この資格のメリットは、在留期間の更新制限がないため、長期的に安定した雇用が期待できる点です。
また、資格取得には、日本語能力試験N2以上の合格が必要で、即戦力としての能力を備えた人材が多い点も特徴です。取得方法には、介護福祉士養成校で学び資格を取得するルートや、「技能実習」や「特定技能」で入国後、介護施設で一定期間働きながら資格を得るルートがあります。
この仕組みにより、介護施設は優秀な外国人労働者の受け入れが可能となり、業界の人材不足解消に寄与しています。
なお、在留資格「介護」については、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事:在留資格「介護」とは?介護分野で働ける在留資格の種類やメリット・デメリットをご紹介!

まとめ
本記事では、介護業界の課題や介護における社会問題、課題解決に向けた取り組みをご紹介しました。
2025年問題とは、日本社会における重要な課題であり、高齢者人口の増加とそれに伴う影響について多方面で議論されています。1947年から1949年に生まれた団塊世代が75歳以上の後期高齢者に到達するため、社会全体の高齢化が加速する見込みです。
高齢者一人暮らしや介護人材の不足、老老介護や認認介護、社会保障の確保不足、そしてヤングケアラー問題など、解決が急務な社会問題が多く挙げられます。
これらの課題に対して、介護職員の業務負担軽減やメンタルケア、長時間労働の解消、IT導入による業務効率化、外国人雇用の促進といった取り組みが進められています。これらの対策は、介護の質を向上させるだけでなく、持続可能な介護体制の構築にもつながるに違いありません。
なお、株式会社グローバルヒューマニー・テックでは、グローバル人材に対する総合的な生活支援を実施しており、外国人の受け入れにおける豊富な経験と知識を有しています。ご相談・お見積りはもちろん無料です。まずはお気軽にお問合せください。⇒株式会社グローバルヒューマニー・テックに相談する