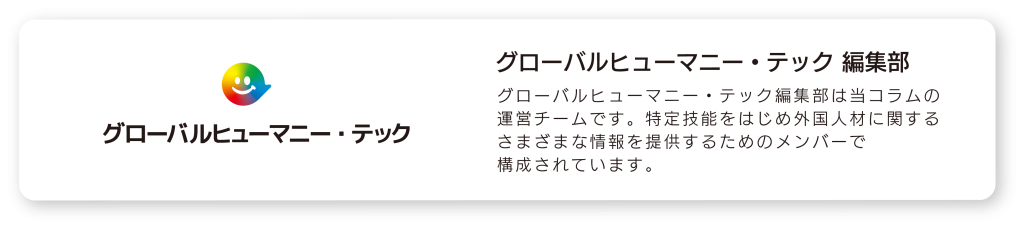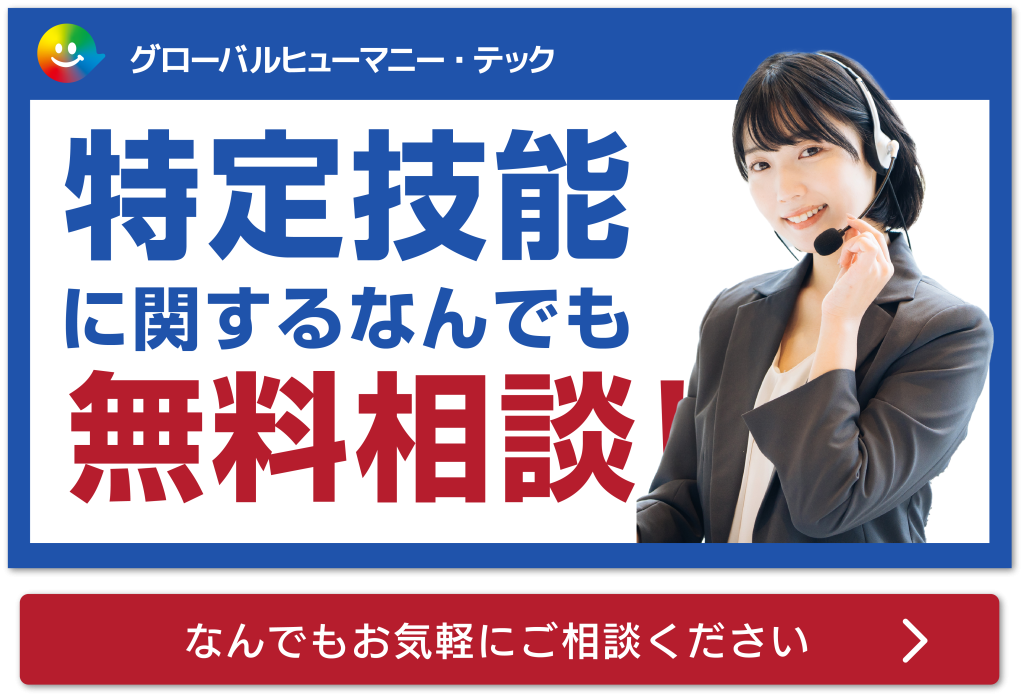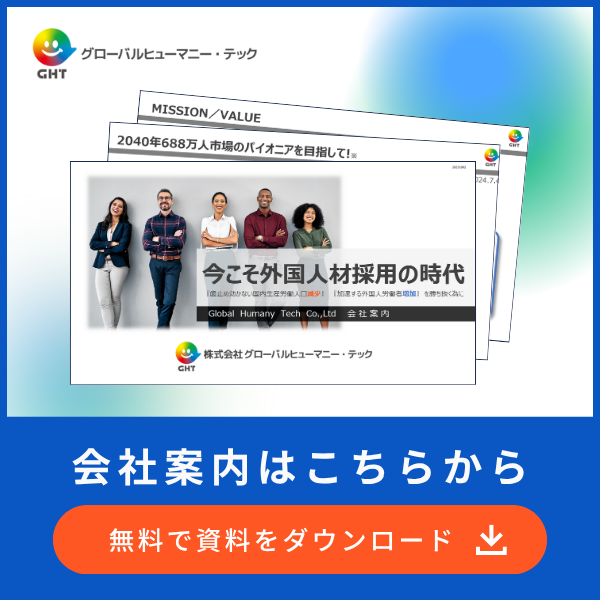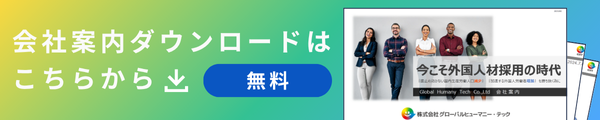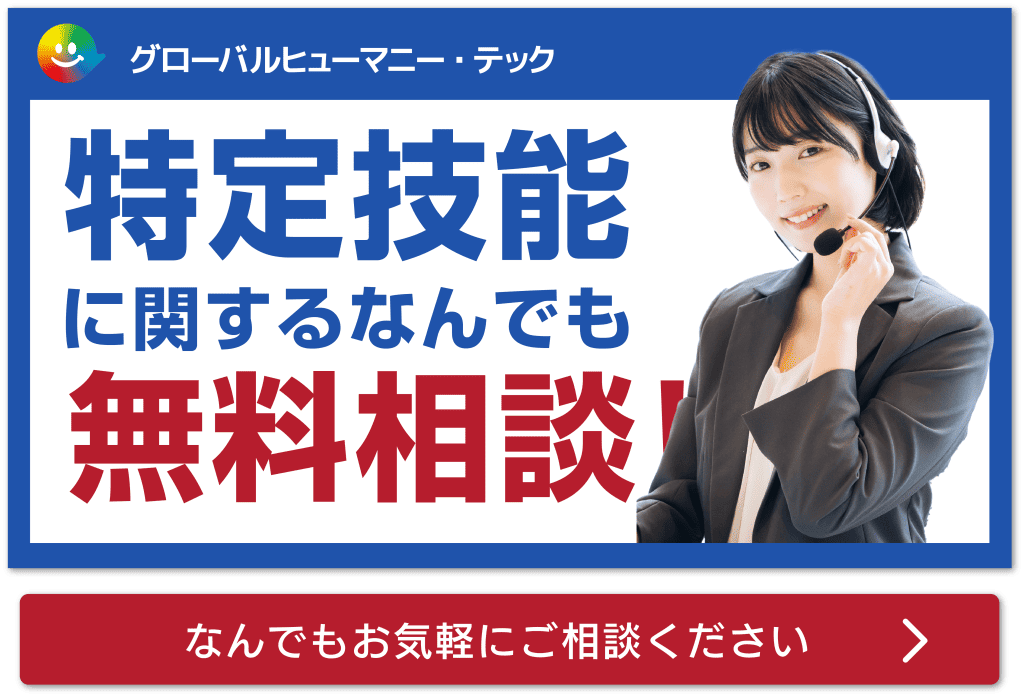オーバーステイ(不法滞在)は、外国人が日本で在留資格の期限を過ぎて滞在し続ける重大な違法行為です。「少しだけなら大丈夫」「うっかり忘れた」では済まされず、強制退去や再入国禁止、企業側の罰則強化など、深刻な結果を招く可能性があります。
本記事では、オーバーステイに該当するケースや罰則、解消方法をご紹介します。また、オーバーステイの外国人雇用を防ぐためのポイントもご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
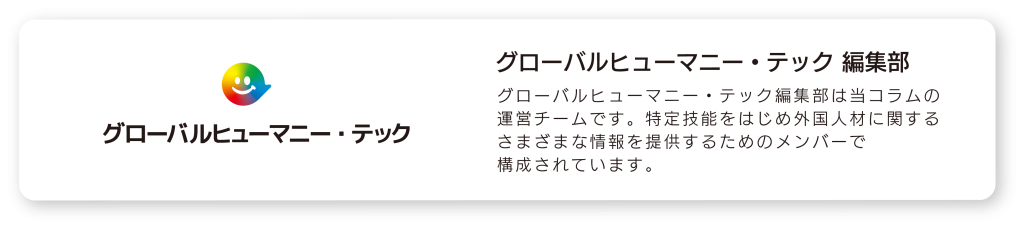
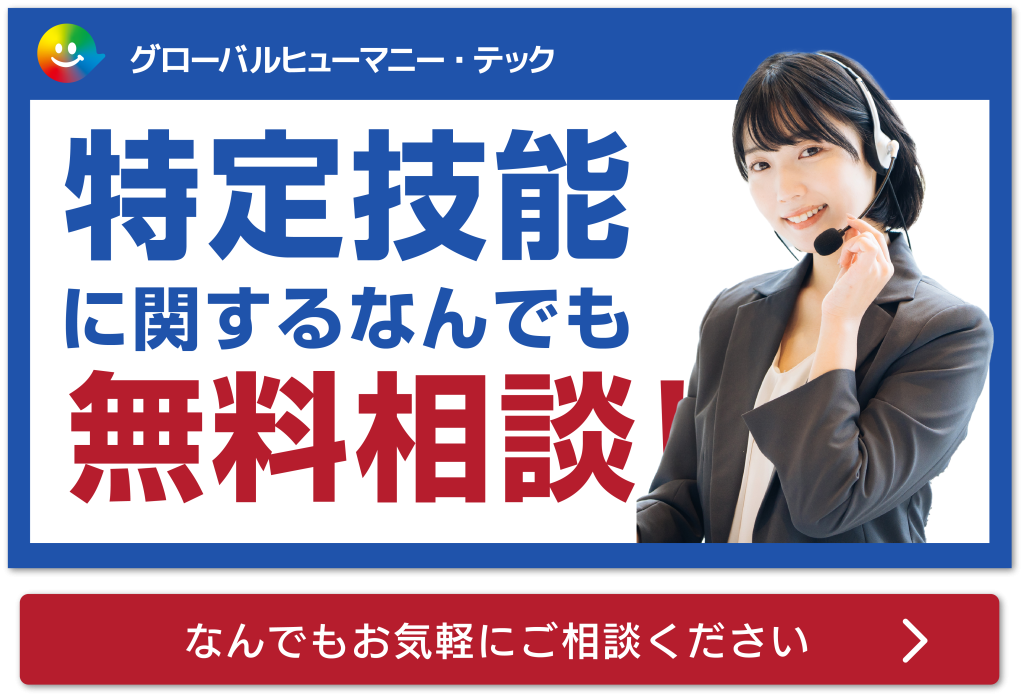
オーバーステイとは?
在留資格を持って日本に入国した外国人であっても、定められた期間を過ぎて滞在を続けると、その行為は不法滞在と見なされます。理由が何であれ、期限を1日でも越えれば法的に違反となり、行政処分の対象になる可能性があります。
たとえ、更新手続きを忘れた場合でも、違法性は免れません。オーバーステイは重大な問題であり、処罰や強制退去など厳しい対応を受けるリスクを伴います。

オーバーステイに該当するケース
次に、オーバーステイに該当するケースについてご紹介します。
- 不法入国で在留している
- 在留期間を超えて滞在している
それぞれの内容について詳しくみていきましょう。
不法入国で在留している
有効なパスポートや査証を持たずに日本に入国する行為は、不法入国とされ、重大な法令違反に該当します。この状態で滞在を続けた場合、発覚すれば強制退去処分の対象となる可能性が高く、以後の入国に厳しい制限がかかる場合もあります。
不法入国と判断された場合は、早急に専門機関に相談し、適切な措置を講じることが大切です。安易な対応は、長期的な不利益を招く結果につながりかねません。
在留期間を超えて滞在している
うっかり在留期間を過ぎてしまうケースは珍しくなく、とくに更新や変更手続きを忘れたことが原因で発生するケースが多いです。しかし、理由の如何にかかわらず、期限を過ぎて日本に滞在している状態は法令違反に該当します。
発覚すれば強制退去の対象となる可能性があるため、できるだけ早く状況を報告し、適切な対応を取ることが大切です。

オーバーステイの罰則
不法就労に関わる企業や関係者には厳しい罰則が設けられていますが、2025年6月から不法就労助長罪の上限が懲役(拘禁刑)5年または罰金500万円に引き上げられ、併科も可能となりました。
また、外国人本人も資格取消しや強制退去の対象となるため、今後の在留や就労に大きな支障をきたすおそれがあります。こうした事態を避けるためにも、企業側は雇用前の確認を徹底しなければなりません。
なお、不法就労助長罪については、こちらの記事で詳しくご紹介しています。
関連記事:【2025年最新】不法就労助長罪の事例3選|外国人を雇用する際に知っておきたいポイントもご紹介!

オーバーステイの解消方法は3つ
次に、オーバーステイの解消方法をご紹介します。
- 退去強制処分
- 出国命令制度
- 在留特別許可
それぞれの内容について詳しくみていきましょう。
1.退去強制処分
退去強制処分は、日本に合法的に滞在するための資格を失った外国人に対し、強制的に出国を命じる措置です。この処分を受けると、初回であっても5年間、再度の場合は10年間にわたり日本への入国が原則として認められなくなります。
さらに、上陸拒否期間が過ぎたとしても、再入国の際には過去の違反歴が審査対象となり、許可が下りないケースも少なくありません。
2.出国命令制度
出国命令制度は、オーバーステイに気付いた外国人が自ら出頭し、速やかに帰国する意志を示した場合に利用できる制度です。この制度を通じて出国した場合、上陸拒否期間は1年と比較的短くなります。
ただし、過去に退去強制や出国命令を受けているケースや、犯罪歴がある場合は対象外となります。また、条件をすべて満たして認定を受ければ、収容の回避も可能です。しかし、再入国には依然として審査がある点には注意が必要です。
3.在留特別許可
在留特別許可は、本来退去すべき外国人に対して、例外的に日本での滞在を認める制度です。日本人の配偶者や日本国籍の子どもがいるなど、人道的な事情がある場合に検討されます。
ただし、許可が与えられるかどうかは法務大臣の裁量に委ねられており、明確な基準は存在しません。また、申請には長期間を要するケースもあり、専門家のサポートが必要になります。

オーバーステイの外国人雇用を防ぐためのポイント
次に、オーバーステイの外国人雇用を防ぐためのポイントをご紹介します。
- 在留カードの確認を徹底する
- 在留期間の更新日を厳守させる
それぞれの内容について詳しくみていきましょう。
在留カードの確認を徹底する
外国人労働者を雇用する際には、在留カードの確認が非常に重要です。採用前に在留カードを提示してもらい、在留資格や在留期間が現在も有効かを必ず確認しましょう。
近年では精巧に作られた偽造在留カードも出回っており、見た目だけでは真偽の判断が困難です。そのため、出入国在留管理庁の「在留カード等番号失効情報照会」システムやICチップ読み取りアプリなどを活用し、正式な在留資格の有無を確認してください。
なお、不法滞在者の特徴と見分け方については、こちらの記事でご紹介しています。
関連記事:不法滞在者の特徴と見分け方とは?外国人を雇用する際に注意すべきポイントを徹底解説!
在留期間の更新日を厳守させる
外国人を雇用する企業にとって、在留期間の更新管理は非常に重要な責務です。更新手続きを怠ると、たとえ数日でも不法滞在と見なされる可能性があるため、早めの準備が欠かせません。
更新を本人だけに任せにせず、企業側でも更新期限を記録し、適切な時期に通知や書類準備の支援を行う体制を整えましょう。二重管理の徹底によってトラブルを未然に防ぎ、外国人労働者が安心して働ける環境を築いてください。

外国人採用の相談に「グローバルヒューマニー・テック」がおすすめな理由
株式会社グローバルヒューマニー・テックでは、グローバル人材に対する総合的な生活支援を実施しています。豊富な実績による盤石なサポート体制とIT技術をかけ合わせた独自のノウハウで、外国人労働者の支援プラットフォームを充実させています。
外国人材の安心安全な採用支援はもちろん、就業支援や生活支援を通じて人手不足をグローバルソリューションで解決するのが私たちの使命です。⇒株式会社グローバルヒューマニー・テックに相談する

オーバーステイ 罰則でよくある3つの質問
最後に、オーバーステイ 罰則でよくある質問をご紹介します。
- 質問1.オーバーステイで不起訴になることはある?
- 質問2.在留カードの更新期限を企業側で管理する方法は?
- 質問3.オーバーステイで日本を出国したら再入国できる?
それぞれの内容について詳しくみていきましょう。
質問1.オーバーステイで不起訴になることはある?
オーバーステイは原則として出入国管理及び難民認定法に違反する行為であり、法的には退去強制の対象となります。しかし、必ずしも刑事罰が科され、起訴されるとは限りません。
とくに、自発的に出頭し速やかな帰国意思を示した場合や、出国命令制度を利用した場合は、刑事罰の対象とならず不起訴処分となるケースが多いです。とはいえ、違法状態であった事実は変わらず、今後の在留資格審査や再入国に影響をおよぼす可能性があります。
質問2.在留カードの更新期限を企業側で管理する方法は?
外国人労働者の在留カードの更新管理は、企業にとっての責務の1つです。手作業や個別管理だけでは、更新忘れや確認漏れのリスクを完全に防ぐのは困難です。そこでおすすめなのが、外国人就労管理システムの活用です。
このようなシステムの導入により、在留カードの有効期限や更新期日を自動で管理し、期限が近づいた際に担当者へ通知する仕組みを構築できます。さらに、出入国在留管理庁の情報と連携し、偽造カードのチェックや在留資格情報の最新状態の確認も可能です。
管理の精度向上だけでなく、担当者の負担軽減や法令遵守体制の強化にもつながります。外国人雇用が増える今、信頼できる管理システムの導入がトラブル防止の鍵になります。
なお、外国人就労管理システムについては、こちらの記事で詳しくご紹介しています。
関連記事:【2025年最新版】外国人雇用管理システムのおすすめ10選|主な機能や選び方もご紹介!
質問3.オーバーステイで日本を出国したら再入国できる?
退去強制や出国命令を受けた場合でも、上陸拒否期間が終了すれば日本への再入国が可能です。この期間は、出国命令の場合は1年、初回の退去強制処分では5年、2回目以降は10年となっています。
ただし、個々の状況によってはこの期間が延長されるケースもあります。自発的にオーバーステイを申告したケースやはじめての違反の場合は、再入国までの待機期間が比較的短く設定されるため、再入国の可能性が高まる傾向にあります。

まとめ
本記事では、オーバーステイに該当するケースや罰則、解消方法、オーバーステイの外国人雇用を防ぐためのポイントをご紹介しました。
オーバーステイは、外国人本人だけでなく雇用する企業にとっても重大なリスクとなります。強制退去や企業側の罰則強化といった厳しい措置を避けるためには、在留カードの確認や在留期間の徹底管理が不可欠です。
トラブルを未然に防ぐには、正確な知識と適切な対応が求められます。外国人雇用や在留管理で不安がある場合は、専門機関や支援サービスの活用を検討しましょう。
なお、株式会社グローバルヒューマニー・テックでは、グローバル人材に対する総合的な生活支援を実施しており、外国人の受け入れにおける豊富な経験と知識を有しています。ご相談・お見積りはもちろん無料です。まずはお気軽にお問合せください。⇒株式会社グローバルヒューマニー・テックに相談する